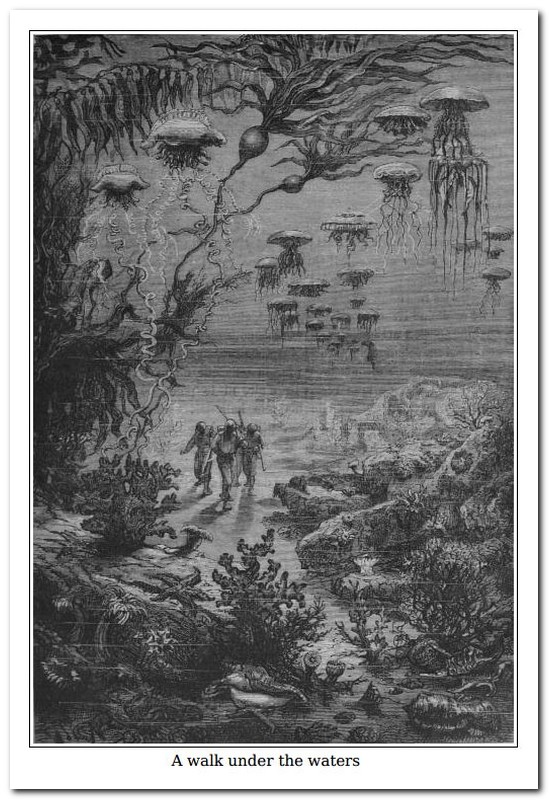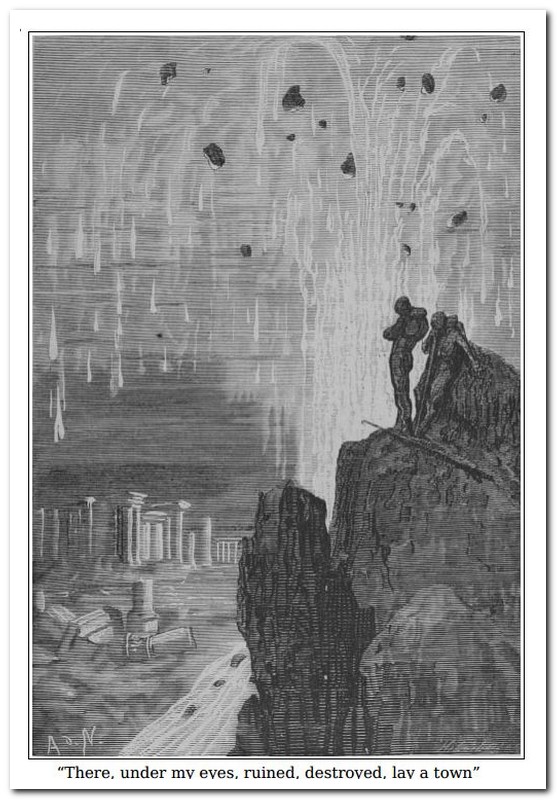私はプログラミング初心者なので、プログラムを書いたり、解説してもらうのに大規模言語モデル(Large Language Model=LLM)がどの程度有効かが知りたいと思いました。ネット検索してみると、九州大学の伊東栄典先生がこちらの動画で、プログラムを書くのに大規模言語モデルChatGPTや Google Bardがどの程度有効かを語っておられますのでご覧になると参考になると思います。
「中級プログラマによる生成AIの活用事例紹介」 伊東 栄典 九州大学情報基盤研究開発センター 准教授
https://youtu.be/7mGbbasLRdM?si=YMw_7uMS0IsDcquL
初級、中級のプログラミングにはこれらはめちゃめちゃ役立つようです。上級レベルになると、質問する人の知識が少ないので適切なプロンプトがつくれなかったり、またLLM自体のの学習データが、上級レベルのプログラミングについては手薄になっているような印象とのことで、上級レベルのプログラムを作ってもらうのに使いこなすのは難しいようです。どんなのが初級、中級、上級かというのは動画をご覧になってください。自分がわからないプログラムコードを入力して説明してくださいと頼むと、ChatGPTが懇切丁寧に説明してくれるのはとても便利ですね。
昔はプログラミングの教科書に練習問題があって、その答えがない教科書は独学している初心者には役立たなかったものです。今やそんな教科書でも練習問題の答えあわせは、ChatGPTなどのLLMで可能になっています。プログラミングではありませんが、私も昔解けなかった数学の教科書の問題をChatGPT (Wolframプラグイン入りにしてあります)にきいてみたところ、なるほどという解答がかえってきたのには感動しました。量子化学や解析力学、分子動力学などを学ぶときにもLLMを併用すると、学習効率が飛躍的に上がると思います。もちろん生化学や糖鎖生物学の学習にも役立ちます。そのへんのところは、ときどきこのブログに書きますので読んでください。
あと英文校正については、いつも紹介している京都大学の柳瀬陽介先生のブログ記事やツイートが役立ちます。
https://yanase-yosuke.blogspot.com/
https://nitter.net/yosukeyanase
また昨日紹介したGPTsで作られた英文校正GPTもいろいろ公開されているようです。最初に知ったのはこちらのツイートでした。
ChatGPTのGPTsで英文校正GPTを作ってみました
アカデミックライティング用の英文校正にカスタムされたGPTです
指示内容も公開しているので適宜改変して自分好みにして頂ければ!
genkAIjokyo|ChatGPTで論文作成と科研費申請 @genkAIjokyo https://t.co/6Tcmthhd1l #note
— 限界助教|ChatGPTで論文作成と科研費申請 (@genkAIjokyo) November 11, 2023
こちらのnoteの記事も書いておられます。
https://note.com/genkaijokyo/n/ndcd52fc2c4b3?sub_rt=share_b