コズミック フロントは面白い番組ですね。今年小学校に入学したばかりの知り合いのお孫さんも、この番組の熱烈なフアンだそうです。幼稚園のころから見ているんですね。こういう番組は、科学に対する理解を深めてくれるのでどんどん放送してもらいたいものです。
さて先日7月13日のコスミックフロント(再放送がBS premiumで7月17日(月) 午後5:00 〜 午後6:00 にあります)は、「天文シミュレーションがコンピューターの世界を変えた!?」というタイトルで、コンピューターでブラックホールの見え方をシミュレートしたり、暗黒物質の分布を探ったりする話から始まりました。そして日本でかつて、20万円ぽっちで、当時の世界最先端のスパコンを越える1テラフロップス(毎秒一兆回の演算)ができる手作りコンピューターを作った話が詳しく紹介されていました。東京大学の杉本大一郎先生のラボで、球状星団の安定性を計算するために一から設計された重力計算専用の手作りスパコンGRAPEの開発エピソードの詳しい紹介です。杉本先生の元で、若い学生さん達ががんばって重力の計算をパイプライン方式ですすめる超高速計算回路を積んだコンピューターを作ったと言う話です。Gravityの計算をPipelineでやることから(Appleコンピューターに対抗して)GRAPEと名付けたそうです。学生さんの中にはあの「栄光なき天才たち」の原作者の伊藤智義さんもいたことがわかります。GRAPE-1のハードウエアは全部伊藤さんが配線もしてこしらえたんですね。その後のGRAPEコンピューターの発展と役割分担、だれがどのように関わったかなどを詳しく番組で紹介していて、大変面白い番組でした。見逃した方は是非、7/17月曜日の再放送でご覧ください。
ちょっとネット検索してみると、伊藤さんの本も見つかりました。
「スーパーコンピューターを20万円で創る」 (集英社新書) 中古本があります。
杉本先生のインタビューはこちらでpdfを無料ダウンロードできます。天文月報の2018年5月号から9月号にインタビューがのっていてpdfをダウンロードできます。2018年の総目次でご覧ください。
https://www.asj.or.jp/geppou/contents/#Yr2018
8月号にGRAPEとエントロピーというインタビューがありますのでご覧ください。
https://www.asj.or.jp/geppou/contents/2018_08.html
面白いインタビューです。
最後になりましたが、伊藤智義さんの「栄光なき天才たち」はお勧めのコミックです。伊藤さんが科学研究者なので、科学者への理解が深いです。これも是非読まれることをお勧めします。
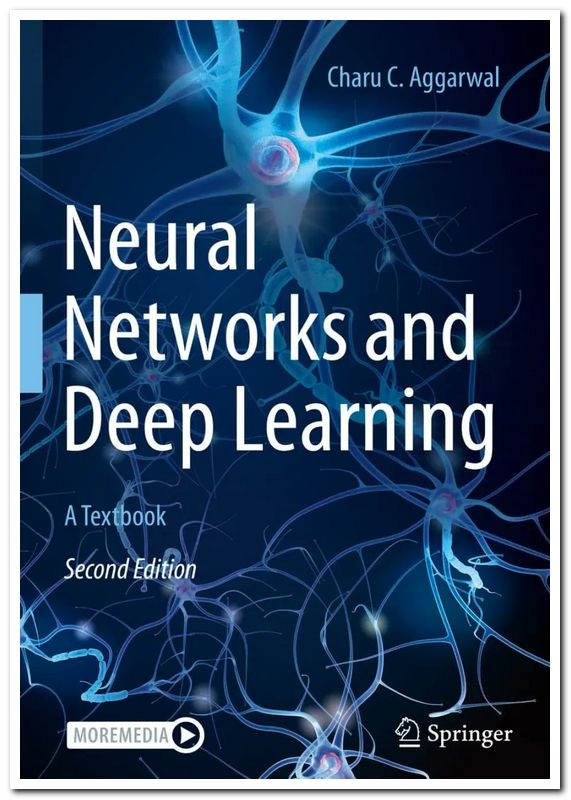 Charu C. Aggarwal 著( Springer Nature 2023 年6月30日発行)
Charu C. Aggarwal 著( Springer Nature 2023 年6月30日発行) 今回は、スタンフォード大学、ワシントン大学、南カリフォルニア大学の統計学者による統計学と機械学習の入門書を紹介します。どちらの本も発行以来、絶大な人気を博している教科書で、日本語訳もすでにでています。今回紹介するのは英語の原著最新版です。最初の本は、
今回は、スタンフォード大学、ワシントン大学、南カリフォルニア大学の統計学者による統計学と機械学習の入門書を紹介します。どちらの本も発行以来、絶大な人気を博している教科書で、日本語訳もすでにでています。今回紹介するのは英語の原著最新版です。最初の本は、