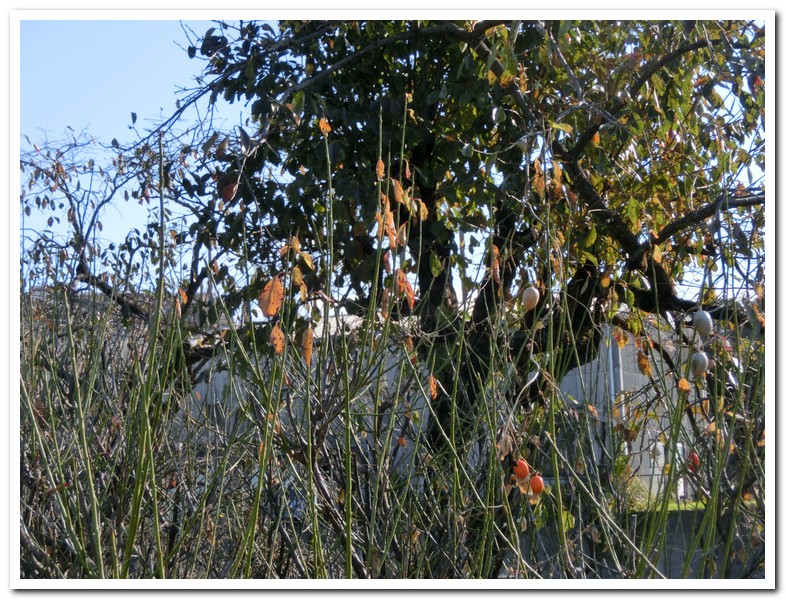このOpen Syllabusというサイトでは無料で、全世界の教育機関.でシラバスに指定されている本を検索できます。著者名や、タイトルや分野名をいれるとどんな本が世界中でどのくらいシラバスに指定されているかの順位がわかります。エクスプローラーというページにはよく引用されている本のトップ一覧がでていてこんな本があるのがわかります。
https://explorer.opensyllabus.org/
第一位はElements of Styleですね。マルクスの共産党宣言、プラトンの国家、フランケンシュタイン、カンタベリー物語、アリストテレスのnなども上位に入っています。
The Elements of Style
William Strunk
Multiple Editions
A Writer’s Reference
Diana Hacker
St. Martin’s / Bedford Books
A Manual for Writers of Term Papers, Theses, and Dissertations
Kate L. Turabian
University of Chicago Press
The Communist Manifesto
Karl Marx
Multiple Editions
The Republic
Plato
Multiple Editions
Calculus
James Stewart
Brooks / Cole
Frankenstein
Mary Wollstonecraft Shelley
Multiple Editions
The Canterbury Tales
Geoffrey Chaucer
Multiple Editions
Nicomachean Ethics
Aristotle
Multiple Editions
Human Anatomy and Physiology
Elaine Nicpon Marieb
Multiple Editions
Doing Your Research Project: A Guide for First-Time Researchers in Education and Social Science
Judith Bell
Open University Press
Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism
Benedict R. O.’G. Anderson
Verso Books
たとえばAuthorで検索したければ、Authorの検索窓で、https://explorer.opensyllabus.org/results-list/authors?size=50
PlatoとかSoseki Natsumeとかいれたりしてどんな結果がでるかみてみると面白いです。Scott GilbertといれるとDevelopmental Biologyの教科書がトップででてきます。
Titlesの検索では、
https://explorer.opensyllabus.org/results-list/titles?size=50
Python ProgrammingとかR programmingなどと入力すると世界中で使われているこれらの言語の教科書の順位がわかります。
サイトにアクセスしていろいろ試してみてください。ただこのリストで注意したいのは、シラバスにのっているものが集められているので新しい教科書や本は順位がものすごく下か、あるいはまったくのっていないことです。たとえばStephen Wolfram (Mathematicaの開発者でセルオートマトンの有名な研究者)で検索すると、2018年の本までしかのっていません。