ChatGPTに関する素晴らしい日本語の動画を紹介します。
【第64回】 大学等におけるオンライン教育とデジタル変革に関するサイバーシンポジウム「教育機関DXシンポ」(4/21 オンライン開催)
「ChatGPTとの付き合い方」中川 裕志 理化学研究所革新知能統合研究センター チームリーダー
国立情報学研究所 – National Institute of Informaticsの動画です。YouTubeでも見ることができます。
https://youtu.be/T6VT7IOocKQ
これは末尾にはりつけてある4月11日に紹介したビデオのシリーズの動画です。国立情報学研究所 の以下のサイトでは、この動画と、スライドの重要部分をpdfにした資料をダウンロードすることができます。
https://www.nii.ac.jp/event/other/decs/past.html
19分ちょっとの動画ですが、ChatGPTを使う心構えや、ChatGPTにまつわる世界的な倫理を含めた取り組み、今後AIとどのようにつきあっていくことになるかという未来予想もある、とてもよい講演です。特に詳細な利用例が参考になります。ChatGPTに、反ワクチンの意見をどのような戦略で普及させたらよいかを教えてもらう例、ローマ帝国の滅亡原因を教えてもらう例とかで、ChatGPTの悪用、誤りを含む回答への対処法なども学べます。さらに今後のこうしたAIが、一律に保守的な意見だけを学習して回答するようになることの危険性も指摘されています。
革新的技術であるChatGPTのようなLarge Language ModelによるAIが今後どのように世界を変えていくか、そこを考えるための基礎がわかる動画です。すぐに見終わることができるので気軽にご覧になることをおすすめします。必見の動画です。
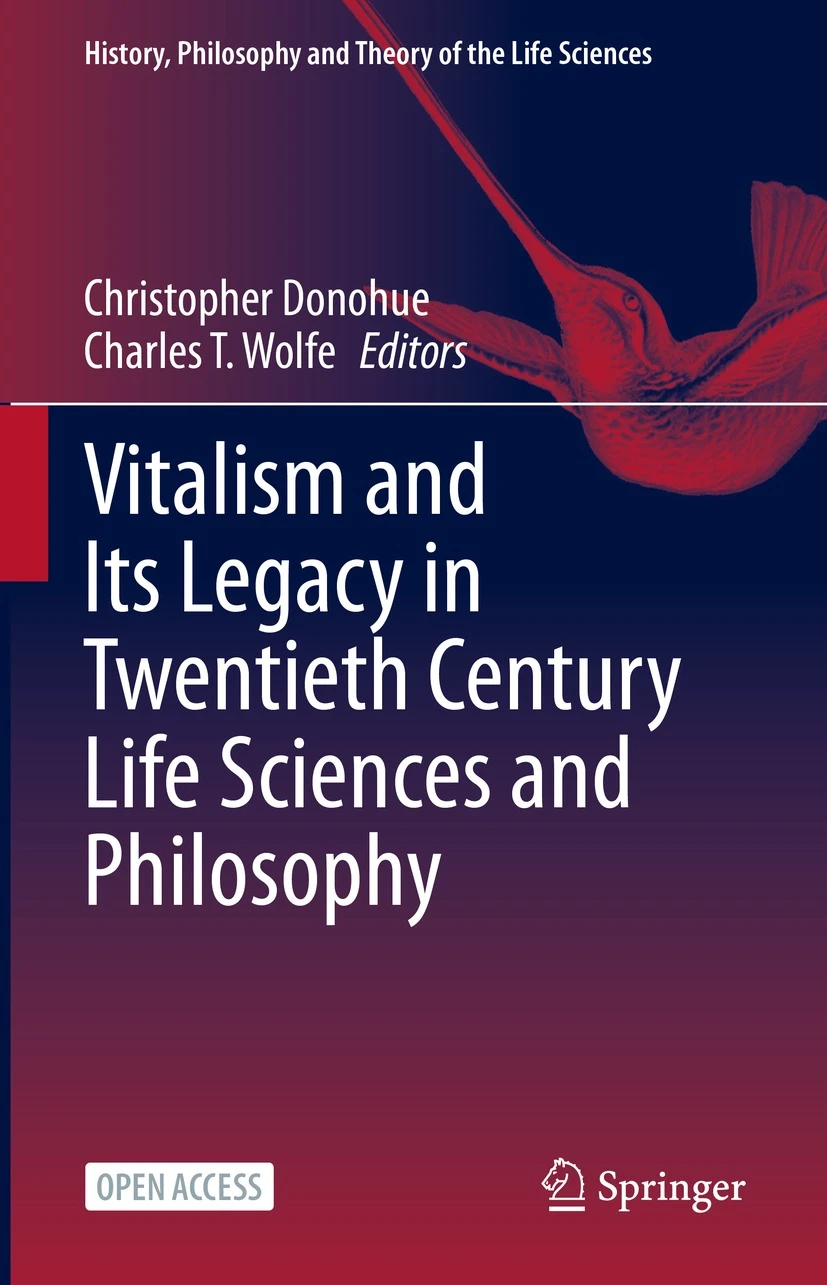 今日はちょっと忙しかったので本の紹介です。生気論というのをご存知ですか。発生学の教科書にでてくる有名な発生学者のハンス・ドリーシュ(Hans Driesch) は「生気論の歴史と理論」という本を書いています。彼の提唱したエンテレキーという概念を中心とした生気論は、この本を訳した米本昌平さんによると、科学界のみならず哲学界からも非科学的な妄説の提唱者として非難され続けたそうです。
今日はちょっと忙しかったので本の紹介です。生気論というのをご存知ですか。発生学の教科書にでてくる有名な発生学者のハンス・ドリーシュ(Hans Driesch) は「生気論の歴史と理論」という本を書いています。彼の提唱したエンテレキーという概念を中心とした生気論は、この本を訳した米本昌平さんによると、科学界のみならず哲学界からも非科学的な妄説の提唱者として非難され続けたそうです。