今日は、英語で無料で読める数学書や講義資料があつめてあるAMSのサイトOpen Math Notesを紹介します。
ASMS はアメリカ数学会American Mathematical Societyの略です。AMSのOpen Math Notesというサイトには無料の英語の数学の教科書や講義資料がいろいろ公開されていて無料でダウンロードできます。
https://www.ams.org/open-math-notes
サイトの左にあるプルダウンメニューから、出版された日付や、トピックス、対象読者(学部生向け、大学院生向け、高校生向け)などで絞り込んで、各種の教材、教科書をダウンロードすることもできます。掲載されている本は、しばらくすると出版されて読めなくなるものもあるので、必要な本や資料がみつかったら、早めにダウンロードすることをおすすめします。
たとえばこんなタイトルがあります。関数解析の最新の教科書です。
https://www.ams.org/open-math-notes/omn-view-listing?listingId=111364
他にも幾つかタイトルをあげておきますす。小中学校の先生むけの現代数学からみた初等数学についての本があります。
Blue Book of Mathematics for Elementary School Teachers (Natasha Rozhkovskaya, Kansas State University)
https://www.ams.org/open-math-notes/omn-view-listing?listingId=111324
In these lectures, we review elementary mathematics within the larger picture of modern mathematics. The main audience of the course are students with prospective careers in elementary school education. The topics include: sets, properties of arithmetic operations, culture of calculations, exponents, decimal and non-decimal base systems, historical numeration systems, GCF(a,b) and LCM(a,b), prime factorization, divisibility tests. Each chapter includes definitions, examples, exercises.
常微分方程式の教科書もあります。https://www.ams.org/open-math-notes/omn-view-listing?listingId=111313
Ordinary Differential Equations: A First Course (Mohammad Niksirat · University of Alberta · Date posted: November 14, 2021 · Date revised: December 26, 2021 )This volume is an elementary textbook on ordinary differential equations that most students in science and engineering faculties take in their second year. All topics in this book are organized into chapters, sections, and subsections. There is at least one solved example for each subject in the book, and most of them are accompanied by graphs and drawing to illustrate the main point visually. The book is self-contained. The appendix chapter summarizes the essential pre-requisite for the course.
他にも線形代数だの確率、論理、高校数学、偏微分方程式、群論や環論、アダマール行列などなどいろんな資料がありますので探してみるとよいでしょう。
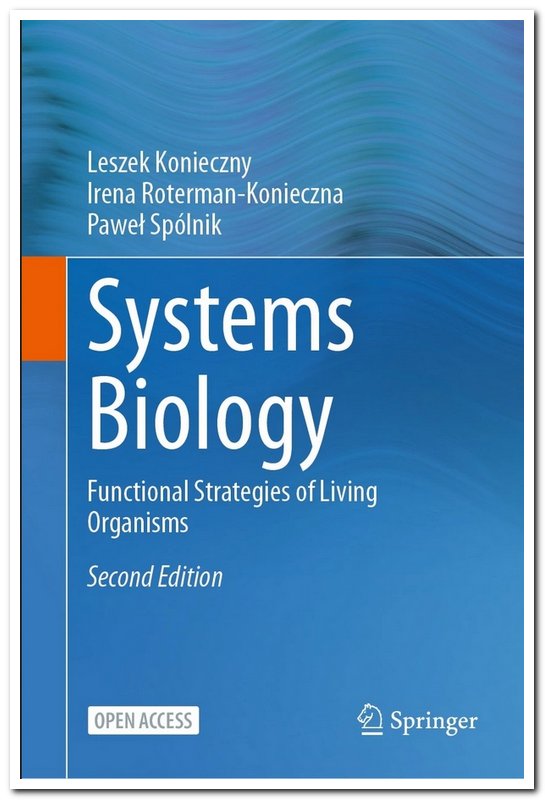 今日は短い記事です。さきほど九大図書館に接続して論文を探していたとき、Springer Linkをみているとオープンアクセスの教科書があるのに気づきました。
今日は短い記事です。さきほど九大図書館に接続して論文を探していたとき、Springer Linkをみているとオープンアクセスの教科書があるのに気づきました。