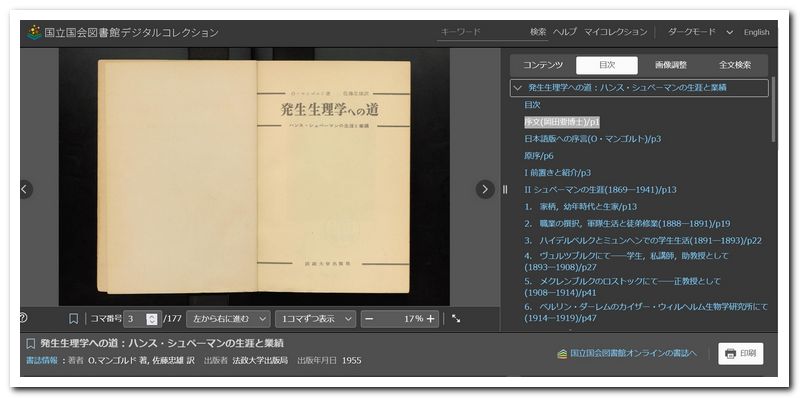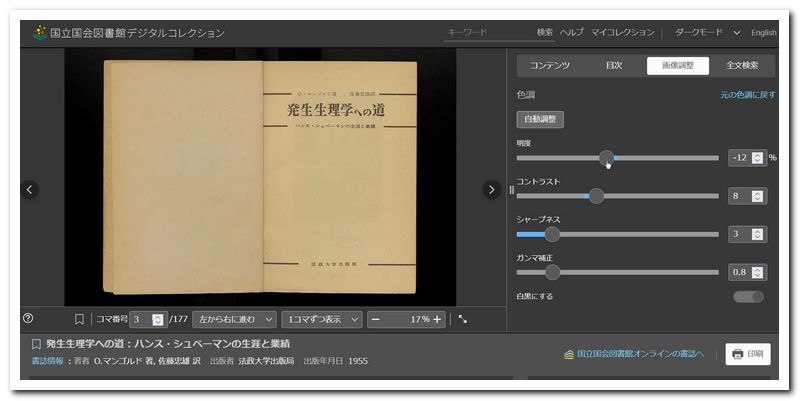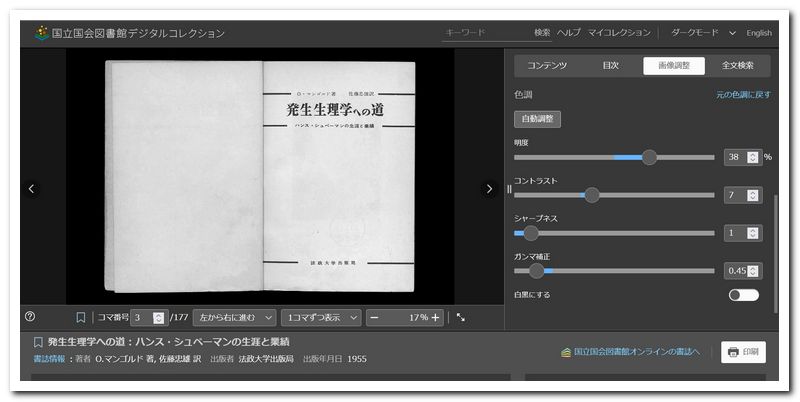超音波は胎児の画像診断に使われていることからもわかるように、超音波は光や赤外線とちがって、透明でない生物体でも深く浸透して画像を得ることができます。最近では超音波を使ってのイメージングや、超音波による細胞への加熱による遺伝子発現制御、超音波による生体内での細胞の移動なども可能になってきいているようです。光ピンセットというのがあってレーザーで細胞や原子などを移動したりトラップしたりできることが知られています。その超音波版もできてきていて、Acoustic tweezers とよばれています。こちらの論文に詳しく書かれています。
https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1813047115
日本語の解説はこちらがわかりやすいです。
https://shiropen.com/seamless/holographic-acoustic-tweezers
動画もあります。https://youtu.be/0Up5kr5Xgcg?si=zKa5Bu7M1tStVFbH
超音波でどうやって物体を浮遊させてトラップできるかの原理は次の動画が必見です。ポリスチレンの小さな白球が次々と空中に浮かぶ様子を見た人は、一目で超音波ピンセットの原理を理解できると思います。
Acoustic Standing Waves and the Levitation of Small Objects
https://youtu.be/XpNbyfxxkWE?si=lOi2km8EEjsUpGvk
後半ではシュリーレン光学系をつかって超音波を可視化して、浮遊している白球が空気の密度の高いところにとどまっていることがわかりやすく示されています。