英語の科学論文の書き方を学べるサイトの紹介です―改訂版―
今まで英語で論文を書こうとする学生、研究者は、次の2つのテーマについて学び、訓練することが必要でした。
・一つは英文法にのっとった英文作る能力の養成で、冠詞の使いわけや時制の使い方などは英語を母国語にしない私達には完璧な習得が難しいスキルです。
・もう一つは、自分が書いた英文を自己添削して、わかりやすく、スーズに読み進められるようなスタイルに改訂する能力の養成です。
後者の英文のスタイルの修正は、英語のnative speakerも学校や講習会で学ぶ技術です。自分の書いた英語論文を自己添削して上手に修正できれば、読みやすく、簡潔で明晰かつ判明な「流れるように内容が頭にはいってくる論文」ができあがるわけです。しかし文法に誤りのない英文を書くだけでも大変なのに、 スタイルと論文のわかりやすさまで考慮するのは、初学者にも熟練した研究者にも大変でした。後者の分野の名著としては、以前の記事で紹介したClarity and Grace (Joseph M. Williams & Joseph Bizup)という本があります。私もこれを読んだ後に書いた論文は見違えるようにわかりやすくなったとほめられたことがあります(今はすっかり忘れてしまったので、また読み直さなくてはと思います)。この本のエッセンスについては、ボストン大学におられる芝孝一郎先生が、ブログで解説しておられます。
英語のオンライン辞書と、英語論文の書き方についてのブログの 紹介です。
芝先生は疫学、因果推論の専門家でボストン大学で活躍しておられる著名な研究者です。今年の夏は因果推論の講義や、英語の書き方の講義などで日本でも大活躍されていました。私は昨日、先生の英文の書き方についての講義を聴講させてもらいました。日本語での講義なのでわかりやすく、極めて役立つ講義を聴かせてもえたと感謝しています。このセミナーシリーズは第一回目だったそうで、これから続々と新しいセミナーが企画されるようで楽しみです。
芝先生の御講演を聞いて思ったのは、ChatGPTが文法チェックをしてくれるので、私達 非英語圏の人間が英文法の習得に苦労する必要はもうないということです。大学受験に必要な程度の英文法を知っておれば十二分であると思われます。最初にあげた一番目のスキル(英文法)の習得には苦労する必要がなくなったので、非英語圏の人間も上の二番目のスキルの習得だけに力を注げばよいことになります。自分の伝えたい内容と意図が誤りなく理解できるようにするテクニック(clarity)と、話のながれがスムーズでつっかかるところがなく読めて容易に理解できる魅力的な文章をつくるテクニック(grace)の習得に集中できるようになったのです。とうとう私達が英語圏の人と対等に論文を書くことができる時代がきたわけです。とうことで、今回の記事では私が芝先生の御講演を聞いてちょっと調べてみた英語圏の大学の論文の書き方についてのサイトをいくつか以下に紹介しておきます。以前のブログ記事で紹介した芝先生のブログもとても参考になりますので、ぜひ読んでみてください。
学部生向きの英語科学論文の書き方の手引き:ハーバード大学版その他について
最初に挿入したブログ記事であげたサイトはこちらです。
Welcome to Style for Students Online by Joe Schall
Effective Technical Writing in the Information Age
https://www.e-education.psu.edu/styleforstudents/
このオンライン教科書の第10章は論文の執筆法についての文献がまとめて紹介されており、それぞれダウンロードできます。
https://www.e-education.psu.edu/styleforstudents/c10.html
いろいろな有用な文献のダウンロードリンクも含まれているのでダウンロードして読んでみてください。このサイトからダウンロードリンクを引用しておきます (ただしリンク切れをなおしてpdfリンクにしておきました)のでご覧ください。
“Comments From the Geological Society of America Bulletin Editors” reviews the pet peeves of journal editors in the geological sciences.
“Advice to Scientist Writers: Beware Old ‘Fallacies’” helps us to reconsider basic writing practices that we sometimes hold as truths when they are not.
“Precise Writing for a Precise Science” is written by a professor of chemistry arguing for the relationship between clear communication and clear science.
“The Universal Recipe, Or How To Get Your Manuscript Accepted By Persnickety Editors” is by a veteran journal editor sharing his insights about what makes a scientific article publishable.
“The Science of Scientific Writing” is a methodical deconstruction of science writing to the point of generating seven practical maxims that science writers can apply to their work.
また次のようなサイトも英語論文のスタイルの勉強には大いに役立ちます。
https://writingcenter.unc.edu/tips-and-tools/
http://www.cs.columbia.edu/~hgs/etc/writing-style.html
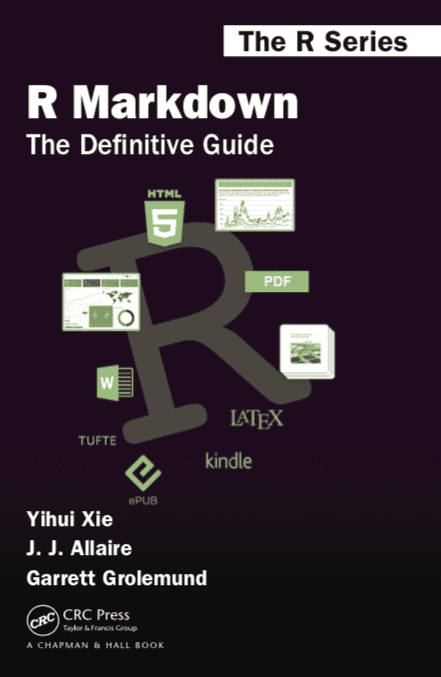 ネットで無料で読めるR markdownの教科書があったので紹介しておきます。
ネットで無料で読めるR markdownの教科書があったので紹介しておきます。