今日は私の使っている辞書ソフトの紹介をしておきます。Windows PCでは
辞書ソフトはシェアウエアのPDICを使っています。http://pdic.la.coocan.jp/unicode/
”書籍版「英辞郎」を購入された方に限り、送金免除になっています。”とのことですので私は送金していません。機能制限なしのシェアウエアです。上記のサイトに書かれているように辞書データは別途インストールする必要があります。私は書籍版の英辞郎(version 144.8以前のデータはプロテクトがかかっていなかったのでPDICに簡単にとりこめました)の付属ディスクからデータをPDICにとりこんで利用しています。ただし、現在の最新版英辞郎や上に述べたバージョン以降の英辞郎(第九版 version 148以降)のデータはプロテクトがかかっているのでPDICにとりこめませんので、誤ってこれらを購入しないように注意してくだい。プロテクトがかかっている英辞郎には、プロテクトされたデータをよみこめる特殊なPDICがついているようです。プロテクトがかかっていない最も新しい辞書データはこちらから購入できます。https://booth.pm/ja/items/777563
安価なのでこれを購入してPDICにとりこめばよいと思います。ただ私はやったことがないので、サイトからテスト用サンプルデータを無料ダウンロードして、PDICにとりこめるのを確認してから購入するようにしてください(と書いたのですが、現在サイトに書いてあるリンクはアクセスできないようです。Firefox, Chromeでクリックすると、You don’t have permission to access this resource.とでるだけです。)サイトに書かれている注意点をあらかじめよく読んでから購入してください。
PDICにはFirefoxあるいはChrome用の機能拡張FirePop!が用意されています。
http://firepop.osdn.jp/
この機能拡張を有効にしておくと、画面の英単語にカーソルをあわせておいてAlt+右クリック(左クリックにも設定変更できます)すると、訳がポップアップします。便利ですので使ってみてください。またPDICはEPWING形式の辞書その他を利用することもできます。ネットで検索すれば、EPWING形式の辞書をPDIC形式の辞書に変換する方法も見つかりますので、辞書の拡張も簡単にできます。
あと、iPadでは次の辞書を使っています。
ウイズダム英和、和英辞典2(物書堂)
Merriam-Webster Dictionary & Thesaurus
この英英辞典は古いバージョンです。英英辞書の中では最高の辞書だと思います。ただ最新版は改悪されています。それで旧版を、時々起動時にバージョンアップのおすすめがでても無視して使い続けています。それで皆さんにはオンライン版の辞書サイトの利用をおすすめします。
https://www.merriam-webster.com/
このサイトを利用すると、私の使っている旧版と同じようにDictioanry とThesaurusが使えることがわかりました。ブックマークして是非活用してください。
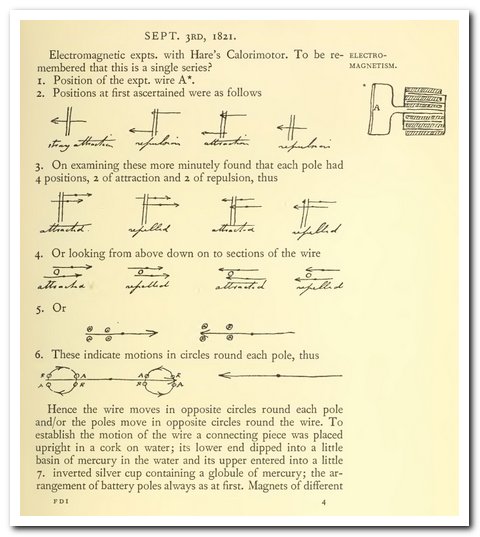
 まだ空色アサガオは毎日咲き続けています。今朝も百余りの花が楽しめました。絞りの朝顔はほとんど種になって来年用の種を集めてかたずけました。しかし庭の芝生にはいつ落ちたのでしょう、小さな絞りの朝顔が花を咲かせ続けています。今日も一日快晴でした。
まだ空色アサガオは毎日咲き続けています。今朝も百余りの花が楽しめました。絞りの朝顔はほとんど種になって来年用の種を集めてかたずけました。しかし庭の芝生にはいつ落ちたのでしょう、小さな絞りの朝顔が花を咲かせ続けています。今日も一日快晴でした。