購入を予約していた電子書籍版「情報の歴史21」(pdf版)を買いました。
これはよい本です。PCでダウンロードしたpdfをiPadに入れてみています。pdfに印刷制限などはかかっていません。このpdf版は、検索できるのが紙の本にない最大の強みでしょう。最強といってもよいと思います。自分の生まれた年には日本と世界でどんなことがあったのかと調べてみました。政治や文化両方の二本と世界についての記載があるので、その時代が良くわかります。赤穂浪士の仇討事件のおこったとき、世界ではなにがおこっていたのか(この頃ニュートンの光学が出版されており、スイフトがいてライプニッツとニュートンが微積分の先取権をめぐって大論争をしていたなど)もわかります。試しにいろんな検索語をいれて、ヒットしたページをみると、さまざまなできごとの相互の網の目のような関係に思い至ることができます。2021年までのデータがはいっているので、CRISPRとかも のっています。日本の人名では、岡田善雄さんとかものっています。(私は大学院生のとき、岡田善雄先生のラボで、当時開発されたばかりの蛍光セルソーターで細胞をわけてもらいに、阪大微研に何度も通っていました。)。HVJ (Sendai virus)による細胞融合の発見者です。詳しくは以下の生命誌研究館のサイトをご覧ください。
https://brh.co.jp/s_library/interview/17/
機械学習というキーワードで検索すると、PyTorchの公開された年まででてきます。ただジョン・ガードンさんはみつけられませんでした。情報の歴史という本のタイトルからすると、コンピュータ関係の歴史年表かと思うかもしれません。この本で情報というのは、生物としての人間が人として生み出してきた情報と、人が社会として生み出してきた情報の全体を言っているように思います。大変すぐれた歴史年表で、検索しては文明の発展と今後につぃていろいろ考えることができる本です。
以前の投稿はこちらです。
 今年の4月に量子力学を全く新しい観点からまとめている本を紹介しました。最近、関連した日本語の教科書をみつけたので紹介しておきます。
今年の4月に量子力学を全く新しい観点からまとめている本を紹介しました。最近、関連した日本語の教科書をみつけたので紹介しておきます。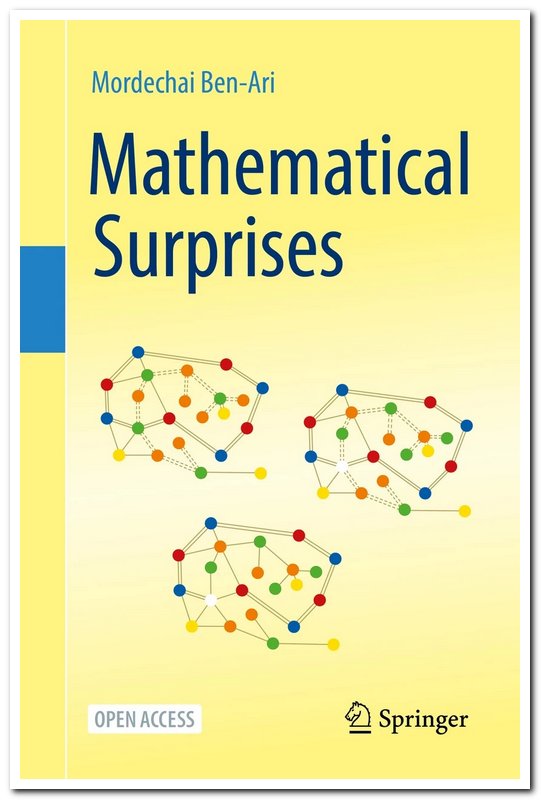 う数学レベルで、多くの驚くような数学の定理や事実を学ぶことができるという本です。
う数学レベルで、多くの驚くような数学の定理や事実を学ぶことができるという本です。