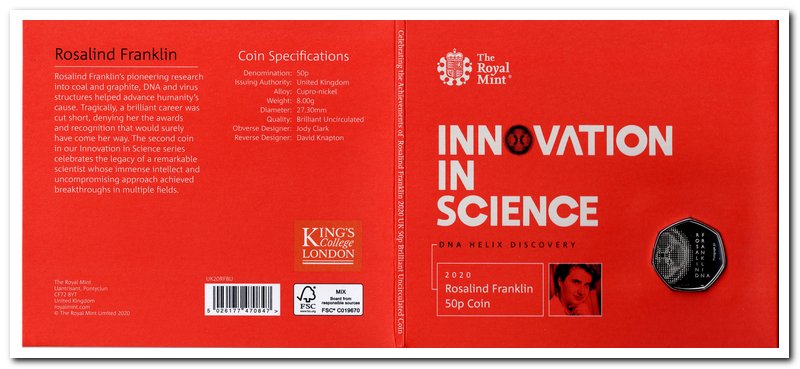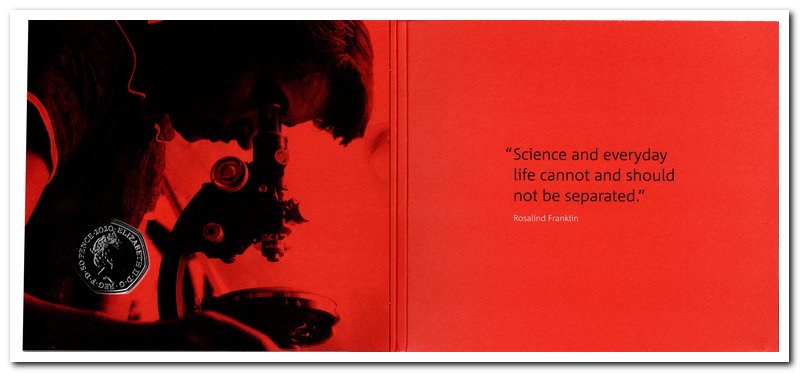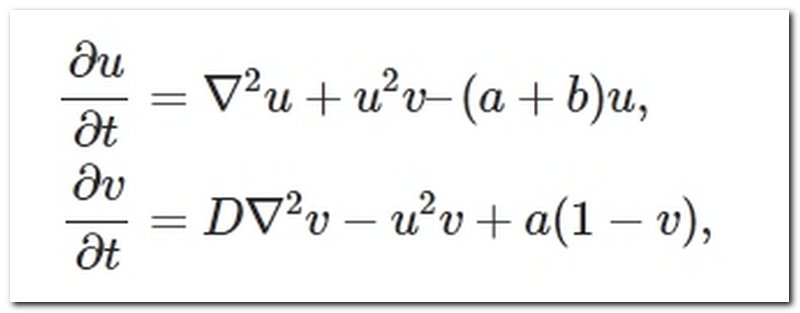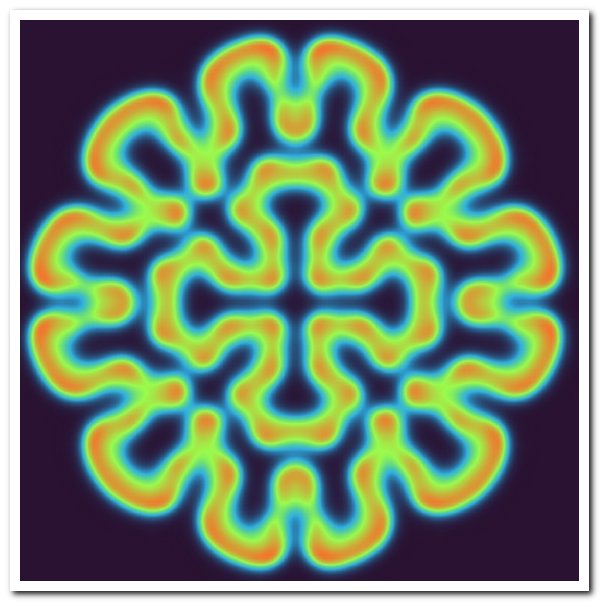ChatGPT のGPT-4で遊んでみました。ChatGPTは俳句をどれくらい理解しているのか試してみたので報告します。
まずは第二次世界大戦前の理化学研究所に滞在していたドイツ人物理学者が詠んだ俳句を採点してもらうことからはじめました。
【私】次の俳句を採点してください。「鎌倉につるがたくさんおりました。」
【ChatGPT】「鎌倉につるがたくさんおりました」というフレーズは、詩的な表現であることは確かですが、伝統的な俳句の形式には従っていません。
伝統的な日本の俳句は、5-7-5の音節パターン(総計17音節)で構成されます。しかし、「鎌倉につるがたくさんおりました」はそのルールを守っていません。このフレーズは「かまくらに つるがたくさん おりました」の11-6-6パターン(合計23音節)になります。また、伝統的な俳句には「季語」と呼ばれる季節の言葉と、カッター(断絶や転換を示す)と呼ばれる要素が含まれています。このフレーズには明確な季語もカッターもありません。したがって、伝統的な俳句の形式に基づくと、このフレーズの採点は低い可能性があります。しかし、詩や自由詩のような他の詩的形式として見れば、それは風景を描写していて美しいと言えるかもしれません。
【私】ではこれはどうでしょう。荒滝や満山の若葉みなふるう。
【ChatGPT】「荒滝や満山の若葉みなふるう」という俳句は、伝統的な5-7-5の音節構成に従っています。
「あらたき や」 – 5音節
「まんざんの わかば」 – 7音節
「みなふるう」 – 5音節
この俳句には、自然や季節の景色を描写する表現が見られ、「若葉」は春の季語と解釈できます。そして、「や」はカッターとして機能し、詩の二部分(「荒滝や」と「満山の若葉みなふるう」)をつなげています。したがって、この俳句は伝統的な俳句の形式に非常によく従っており、高い評価を受けるでしょう。しかし、最終的な採点は、詩の内容、感情、意味などをどのように解釈するかによる部分もあります。
【私】的確な採点だと思います。これは夏目漱石の句です。では かまきりがヒガンバナにのぼってこっちを見ている情景を描写している俳句をつくってみてください。
【ChatGPT】素晴らしいテーマを提供していただきありがとうございます。次のように作ってみました:
「ヒガン花 カマキリ挑む 秋の眼」
【私】(Regenerate Responseボタンを押しました)
【ChatGPT】あなたのリクエストに基づいて以下のように作成してみました:
「秋風やヒガンバナに昇るカマキリ」
この句では、季語として「秋風」を使用し、秋の季節を示しています。また、「や」を使用して詩の二部分(「秋風や」と「ヒガンバナに昇るカマキリ」)をつなげています。カマキリがヒガンバナに登っているという描写は、情景を具体的に思い描くのに役立つ詳細です。
【私】(もう一回Regenerate Responseボタンを押しました)
【ChatGPT】素晴らしいテーマですね。以下にご提案します:
「秋風に カマキリ登り 彼岸花」
この句は秋風(”あきかぜ”)と彼岸花(”ひがんばな”)、そしてその上に登るカマキリという景色を描いています。また、「秋風」は秋の季語として機能しています。
【私】最後の句が一番気に入りました。ありがとう。
【ChatGPT】とてもうれしいです、お気に召していただけたようで。日本の美しい自然と季節を俳句で表現することは、本当に素晴らしい体験ですね。何か他に質問がありましたら、いつでもお気軽にどうぞ。ありがとうございました!
ChatGPTは日本語でも結構人間らしい応答をしますね。ただ俳句を批評するほうが、詠むよりはずっと得意であるという印象でした。俳句を作るときのブレーンストーミングには使えるかもしれません。俳句のテキストを十分に学習させたLLMならきっと驚異的な能力を発揮するのではないでしょうか。
後書き:「鎌倉に鶴がたくさんおりました」 というのは、オットー・ラポルテ(Otto_Laporte)というドイツ人(後、アメリカに帰化)の俳句です。
これは岡潔が著書で紹介していた作品です。著書で読んだのですがどの本か思い出せないのでGoogle検索でみつけた岡潔の講演録から引用します。http://www.okakiyoshi-ken.jp/oka-18-04.html
「日本は、明治以前と以後とでたいへん変わっているのです。明治以後の日本は、西洋の思想をとり入れ、その中に住んでいると申しました。日本語も、実質的には西洋の言葉になってしまっている。
終戦前、それもだいぶん前、物理の寺田先生がまだ理研をやっておられた頃の話ですが、その頃ドイツにオットー・ラポルテという理論物理学者がいた。まだ30前だけれども、スベクトル分析でたいへんよい仕事をした。それで理研はこれを招聘した。ラポルテ氏は寺田先生の教室へ入った。
ところで、ここは俳句が盛んでした。みんな寄って俳句というものを教えた。そうして鎌倉へ旅行した。そうすると、ラポルテ氏は帰ってきて、みんなに俳句をよんだといって示した。その俳句が「鎌倉に鶴がたくさんおりました」。これではどうにも仕方がない。まるで俳句にならない。そう思うでしょう。これは欧米語ですね。」
ここでいう寺田先生は、寺田寅彦です。このオットー・ラポルテという学者は、ハイゼンベルクとパウリの親しい友人で学生時代に3人で自転車旅行をしたりしています。ハイゼンベルクとパウリを仲介する役割を果たして、その後の量子力学の発展に大きな役割を果たしたそうです。彼自身もゾンマーフェルト門下の優秀な理論物理学者です。量子力学、電磁気学、分光学、流体力学で大きな業績をあげ方です。(Wikipediaはこちら。https://en.wikipedia.org/wiki/Otto_Laporte 彼のことは、ハイゼンベルクの書いた本「部分と全体」邦訳47ページなどにも登場します)。Wikipediaによると、日本に来たのは1928年京都大学、1933年と1937年でこの滞在中に日本語を話せるようになり、日本文化への理解を深めたそうです。戦後は日本とアメリカの原子力協定の締結にも働いたそうです。