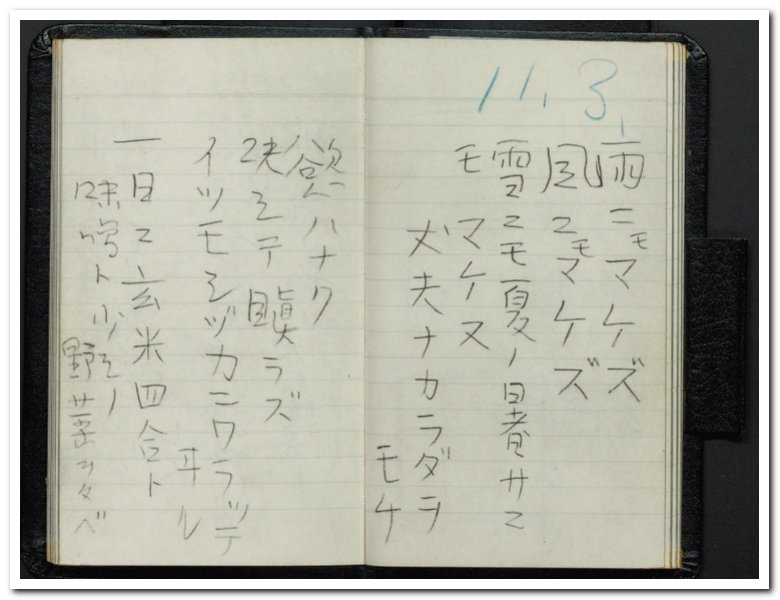昨年、京都大学で英語ライティング、リスニングを教えておられる柳瀬 陽介先生のブログを紹介しました。
DeepL, Grammarly, WordTuneを連携して英文を書く時代になったという記事でしたが、ChatGPTが出現した現在、英語教育はどのように変わったのでしょうか。今日、久しぶりに先生のサイトを拝見しました。ChatGPTで英語教育が革命的に変化しつつあることが実感できまので、以下のリンクにある、先生のブログをご覧になることを薦めます。
https://yanase-yosuke.blogspot.com/
先生のブログには、英語で論文を書く必要がある私達にとって、ものすごく役立つChatGPT用のプロンプトが公開されているので、是非使ってみて英語の学習を効率化してみてください。https://yanase-yosuke.blogspot.com/2023/05/chatgptver2.html
この記事から少し引用します。
「このプロンプトは、学習者(大学レベル以上)が学術英語執筆を自学自習することを助けます。
下のプロンプトの指定欄に英文を入れると、ChatGPTが以下の6つを出力します。
1) 入力したオリジナル英文
2) 語法(=文法・句読点・綴り)だけを添削した英文
3) その語法添削のポイント
4) 語法添削した英文をさらに文体的に改善した改訂英文
5) その英文改訂のポイント
6) 英文執筆者へのコメント
<中略>
なお、このプロンプトはChatGPTのGPT-4を前提としていますが、GPT-3.5でもBingでもBardでも使えます。下にその出力例をつけていますが、GPT-3.5とBardの出力の質は低いです」とのことです。
この記事のプロンプトは英語での指示で、実際の使用例がのっています。大変役立つプロンプトですので、是非自分の英文に使ってみてください。とうとう日本人が英語で論文を書くときの障壁が消えましたね。英文校閲に余分な時間をかける時代が終わりました。余分な時間と費用をかけずに、各自のすばらしいアイデア、研究成果をどんどん英語で発信できるようになりました。まさに革命ですね。
なお、このブログで柳瀬先生は高校生向けの英作文学習用のプロンプトも公開してくださっています。
https://yanase-yosuke.blogspot.com/2023/05/chatgptbing.html
先生のTwitterにも高校生用のプロンプト(中学生でも使えるようにプロンプトを変更する方法も載っています)の紹介がありますので、「Twitterで会話をすべて読む」の部分をクリックして連続ツイートを読んでみてください。こんなふうにプロンプトが使えるんですね。すばらしい記事でした。
【拡散希望】ChatGPT/Bingが高校生に英文添削・改訂を出力し、日本語で解説を加えるプロンプトを作りました。中高生に英語を指導されている皆さん、このプロンプトの効果や限界などをご教示いただけたら幸いです。可能な限りプロンプトを改善してゆきたいと思っています。 https://t.co/3uYG1EjA3W
— Yosuke YANASE (柳瀬陽介) (@yosukeyanase) May 30, 2023
以前のブログの記事も、以下に再録しておきます。
2022/1/10
京都大学で英語ライティング、リスニングを教えておられる柳瀬 陽介先生のブログを知りました。今や英文ライティングは機械翻訳の利用が上式だそうです。解説動画「機械翻訳によって、異文化の問題は前景化するのかそれとも後景化するのか:一般学術目的の英語ライティング授業からの考察」
https://yanase-yosuke.blogspot.com/2021/11/をご覧ください。動画は
https://www.youtube.com/watch?v=piaM2RDBwysでも見られます。講演が行われたシンポジュウムの他の先生の動画は以下からみられます。機械翻訳や英語の国際語化につぃての問題点など大変参考になる講演がきけます。
https://sites.google.com/view/125th-sympo-language-education/schedule
英文ライティングで機械翻訳を利用するのはもう常識になっているそうです。次の記事にはDeepL, Grammarly, WordTuneを連携して英文を書く方法について書かれていて参考になります。
https://yanase-yosuke.blogspot.com/2021/04/wordtune10-ai.html
あと、英語学習全般についてのアドバイスも以下にあります。
「知的な英語を使いこなせるようになりたい大学生のために 」という記事です。https://yanase-yosuke.blogspot.com/2019/06/blog-post.html