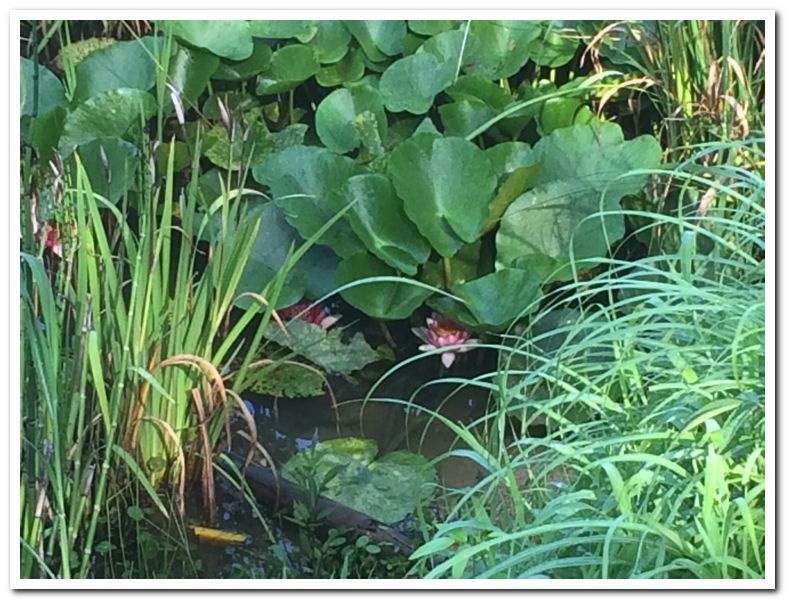本日のカレントアウエアネスポータル(国立国会図書館のポータルサイトです https://current.ndl.go.jp/)に
「アカデミックライティングにおけるChatGPTの活用法(文献紹介)」という記事がでました。
https://current.ndl.go.jp/car/186055
これはPerspectives on Medical Educationというオランダで発行されているオープンアクセスの雑誌の最新号にのった次の記事の紹介です。
Lingard L. Writing with ChatGPT: An Illustration of its Capacity, Limitations & Implications for Academic Writers. Perspectives on Medical Education. 2023, 12(1),p. 261?270.
https://doi.org/10.5334/pme.1072
オープンアクセスなので、論文をダウンロードしてざっと論文を読んでみました。この論文にはChatGPTのプロンプトの使い方の例が詳細に書かれているので大変役立ちます。自分の目的に合致するChatGPTの応答を導くためには、どのようにChatGPTと対話をすすめていくとよいかが、例を挙げてあるのでとてもよくわかります。各自の目的に応じてプロンプトは自作するのがよいのですが、プロンプト自作の要点がよくわかる論文です。
論文にはChatGPTが、文献をでっちあげたりすることがよくあることも書かれていて、例も挙げてあって具体的によくわかります。
また論文執筆時のパラグラフを改良するにもChatGPTが使える例もあげてあります。left-branching sentencesとright-branching sentencesというのを知っていますか? 最初に例などをいろいろあげる文を並べた後に、結論の文が並んでいるのが、left-branching sentencesです。パラグラフの左の方に、ごちゃごちゃと枝葉末節みたいに文が並んでいることから、left-branching sentencesといいます。これとは逆に、結論の文が最初で。結論に関する説明やデータの文が後に並んでいるのを、right-branching sentencesというのです。left-branching sentencesは読者にわかりにくいので、ChatGPTに(プロンプトで)お願いして、right-branching sentencesに変えてもらう例が詳しくこの論文胃書いてあります。文法チェックや論文のスタイルの変更も、うまくプロンプトをつかいながらChatGPTにやらせることもできるのです。面白いことに、ChatGPTはleft-branching sentencesとright-branching sentencesの意味を逆に思い込んでいたようで、最初は真逆の説明をしていたそうです。著者がプロンプトで誤りを指摘すると、ChatGPTは謝ってきます。ChatGPTの誤りを訂正した後、スタイルの変更をさせる例が載っていて大変参考になります。ChatGPTと対話しながら、最適の応答をかえしてくるように導いていくテクニックがいろいろな例について詳細に書かれているので、これは必読の論文だと思います。
さらに、最後の方には、私達のように英語を母国語としない論文著者が英文を書くのに、ChatGPTはとても役立つとも書かれています。皆さんもこの論文などを読んで、ChatGPTを活用することで、成果や意見をどんどん発表していってください!
付記;この論文はThe Writer’s Craftというカテゴリーの記事です。トップページの検索窓にWriter’s Craftなどといれてこの雑誌の記事を検索してみてください。論文の書き方についての有用な記事や、レフリーのやり方、論文へのコメントの仕方など大変有用な発信法jに関する記事がヒットします。
今日検索したところでは、以下のようなタイトルの記事が読めるのがわかります。役立ちそうですね。興味のある記事から読んでみてください。The Writer’s Craftと検索窓にいれて、Theをつけて検索するともっとヒットしますが、あまり関係のなさそうな記事もヒットするようです。
When English clashes with other languages: Insights and cautions from the Writer’s Craft series
The story behind the synthesis: writing an effective introduction to your scoping review
Collaborative writing: Strategies and activities for writing productively together
Writing for the reader: Using reader expectation principles to maximize clarity
Developing and piloting a well-being program for hospital-based physicians
Pace, pause & silence: Creating emphasis & suspense in your writing
Don’t be reviewer 2! Reflections on writing effective peer review comments
The academic hedge Part I: Modal tuning in your research writing
Giving feedback on others’ writing
From semi-conscious to strategic paragraphing
Beyond the default colon: Effective use of quotes in qualitative research
Writing an effective literature review: Part I: Mapping the gap
Writing an effective literature review: Part II: Citation technique
Using rhetorical appeals to credibility, logic, and emotions to increase your persuasiveness
Expressive instructions: ethnographic insights into the creativity and improvisation entailed in teaching physical skills to medical students
Mastering the sentence
To fail is human: remediating remediation in medical education
Tuning your writing
Taking presentations seriously: Invoking narrative craft in academic talks
Get control of your commas
Does your discussion realize its potential?
Physicians’ professional performance: an occupational health psychology perspective
Academic promotion packages: crafting connotative frames
Bonfire red titles
The writer’s craft
Enlisting the power of the verb
The three ‘S’s of editing: story, structure, and style
The art of limitations
Avoiding prepositional pile-up
Joining a conversation: the problem/gap/hook heuristic
The power of parallel structure
Beyond feedback: 11 tips for coaching writing
Strategic Paragraphing 2.0: Techniques for Enhancing Inter-Paragraph Coherence
Metacommentary: Identifying and Mastering ‘Dear Reader’ Moments
The Art of Revising
Writing with ChatGPT: An illustration of its capacity, limitations & implications for academic writers