R Markdownというのを聞いたことがありますか?これで論文を書いて、できた原稿をWordの原稿やpdfあるいはPower Point ファイルなどに自由に変換することもできます。本を書くことも出来るそうです。
データ解析をRで行った後、できたグラフを論文やレポートに貼り付けて仕事を完成させるのは普通に行われている作業です。しかしこの貼り付けると言う作業があるため、できた論文原稿やレポートにのっているグラフや表が、どんなRのプログラムやスクリプトで作られたかがわからなくなることがあります。よくあるこうしたトラブルを避けるには、レポートや論文原稿の内部に、Rでどんな解析をしたかをプログラムやスクリプトごと書き込んでおけばよいわけです。Rマークダウンは、Rのプログラムと普通の文書を同時にレポートにうめこんでおき、必要なときにpdfやdocxファイル、パワーポイントファイルなどなどを一発で生成できる道具です。RStudioからR Markdownが使えるので、だれでも簡単に再現性のあるデータ解析結果のレポートをつくることができます。これを使えば、一番最初に書いたような、このグラフを作ったR のプログラムを探す必要がなくなりますので、完璧に再現性のあるレポートを作ることができます。本としては、おすすめは
「再現可能性のすゝめ―RStudioによるデータ解析とレポート作成― (高橋 康介著)」共立出版です。
https://www.kyoritsu-pub.co.jp/bookdetail/9784320112438
この本の第一章が特に再現可能性の必要性についてわかりやすく書かれており、なぜRマークダウンが必要かがよくのみこめます。この本を買う前に、次のスライドやリンクで概要をつかめるのでまずこれらのリンクをたどってみてください。
R Markdown 入門 (Tokyo.R #91) https://rpubs.com/ktgrstsh/755893
R ユーザー以外も知るべき R Markdown 入門/Introduction-to-R-markdown-for-Everyone https://speakerdeck.com/ktgrstsh/introduction-to-r-markdown-for-everyone?slide=3
TokyoR98 RMarkdown入門 Visual modeではじめよう (niszet, @niszet0)
https://nitter.net/tech_slideshare/status/1522109628125179904
このスライド末尾のほうにいろんな入門サイトのリンクがありますので大変参考になります。
 MRC LMB (英国ケンブリッジ)ではThe 2022 Introduction to Biophysical Techniques lecture seriesというのをやっています。
MRC LMB (英国ケンブリッジ)ではThe 2022 Introduction to Biophysical Techniques lecture seriesというのをやっています。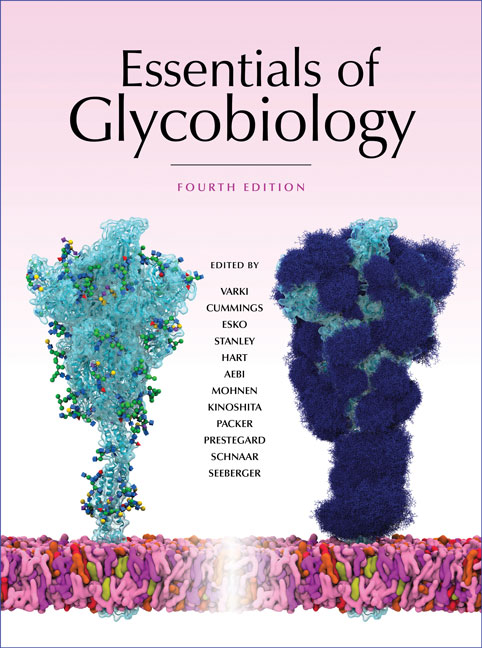
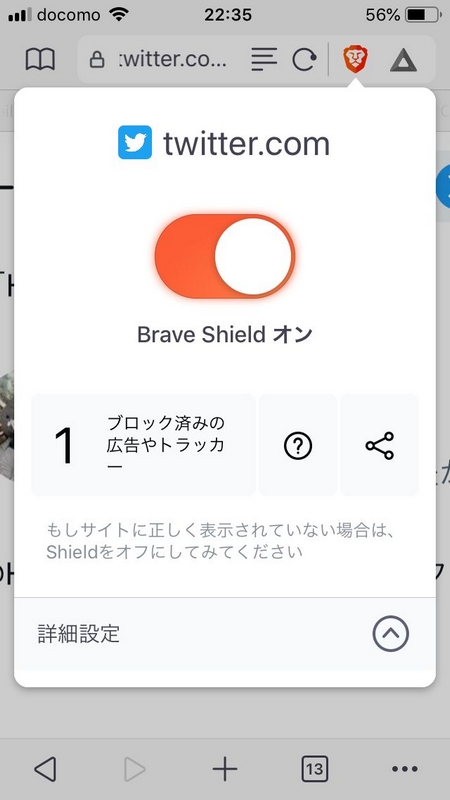
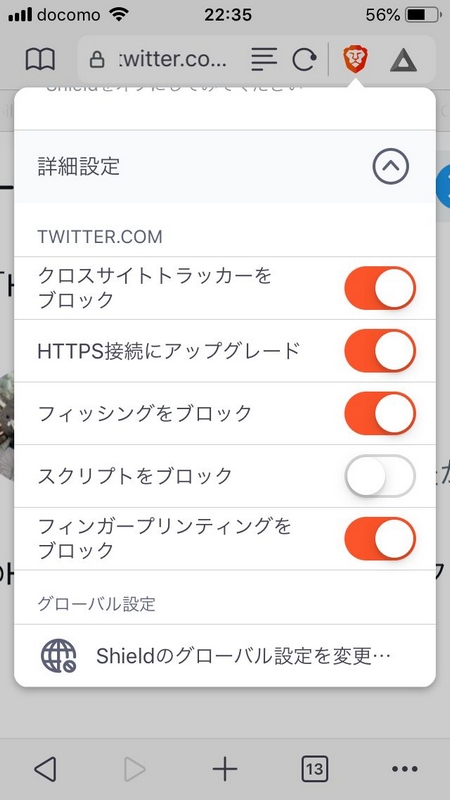
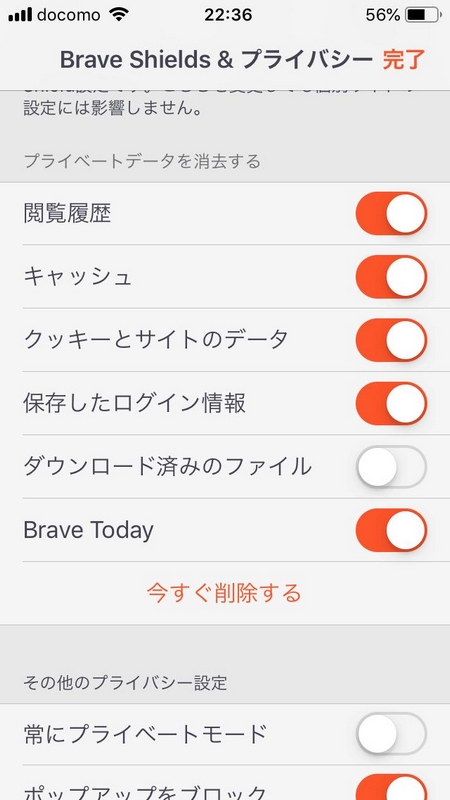
 余談になりますが、先生が
余談になりますが、先生が 今日は科学とは関係のない話の紹介です。私の母から聞いた話です。母は幼いときに実母を病気でなくし、すぐ継母がきて奉公にだされたそうです。母が7歳の時、母のお母さん(当時29歳)が病気で亡くなる日のことでした。親戚が集まっており、私の母は病気のお母さんの隣の部屋で親戚の人に寝かしつけられていたそうです。眠っていた母がふと目をあけると、ふすまのところにお母さんが立っているので、「おかあちゃん元気にならはったんや!」、「おかあちゃんがそこに立ったはるやん!」と喜びの声をあげたそうです。しかし大人には何も見えていないようで、大人たちが、ものすごく怖がっていたと、母が話してくれました。私の母のお母さんはその日に亡くなったのでした。私の京都の家には、私の母のお母さんの位牌がありました。母が毎日その位牌に御線香をあげて手を合わせていたのを覚えています。私の母が亡くなった後、母の位牌も作って仏壇に並べたのですが、片付けているときに二つの位牌の裏を見て驚きました。私の母の命日と、母のお母さんの命日は同じだったのです。年末も近い、寒い京都の冬の日でした。
今日は科学とは関係のない話の紹介です。私の母から聞いた話です。母は幼いときに実母を病気でなくし、すぐ継母がきて奉公にだされたそうです。母が7歳の時、母のお母さん(当時29歳)が病気で亡くなる日のことでした。親戚が集まっており、私の母は病気のお母さんの隣の部屋で親戚の人に寝かしつけられていたそうです。眠っていた母がふと目をあけると、ふすまのところにお母さんが立っているので、「おかあちゃん元気にならはったんや!」、「おかあちゃんがそこに立ったはるやん!」と喜びの声をあげたそうです。しかし大人には何も見えていないようで、大人たちが、ものすごく怖がっていたと、母が話してくれました。私の母のお母さんはその日に亡くなったのでした。私の京都の家には、私の母のお母さんの位牌がありました。母が毎日その位牌に御線香をあげて手を合わせていたのを覚えています。私の母が亡くなった後、母の位牌も作って仏壇に並べたのですが、片付けているときに二つの位牌の裏を見て驚きました。私の母の命日と、母のお母さんの命日は同じだったのです。年末も近い、寒い京都の冬の日でした。