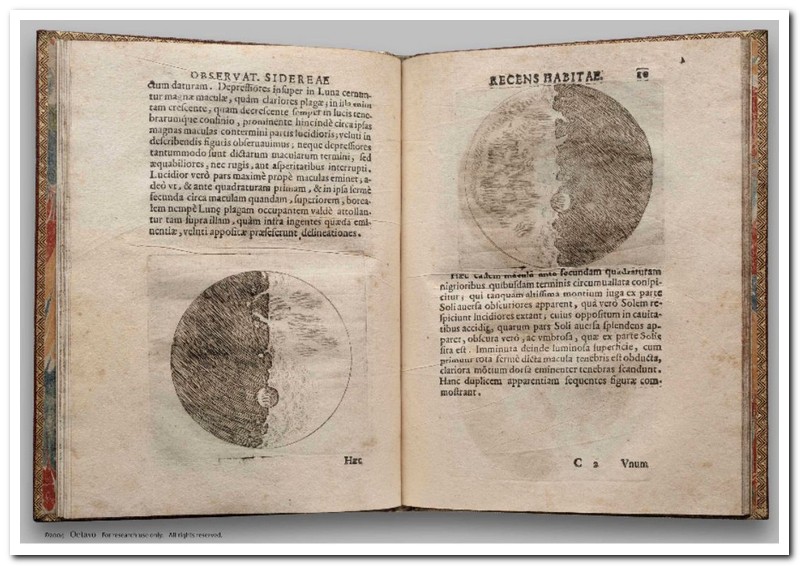今、NHKオンデマンドに試しに加入してみて毎日100分de名著を見ています。先日は、「赤毛のアン」と、「アルプスの少女ハイジ」がおすすめの回だという記事を書きました。
「赤毛のアン」や、「アルプスの少女ハイジ」をとりあげたNHKの100分de名著はおすすめです。
マキャベリの「君主論」、パスカルの「パンセ」、「般若心経」、ハイデガーの「存在と時間」、岡倉天心の「茶の本」、レムの「ソラリス」、夏目漱石スペシャルとか小松左京の作品、宮沢賢治スペシャルや「銀河鉄道の夜」、ユング心理学の河合 隼雄特集などいろいろな名著がとりあげられています。
リストはNHKのこちらのサイトでみられます。https://www.nhk.jp/p/meicho/ts/XZGWLG117Y/list/
こうした本のほとんどは、国立国会図書館の個人送信資料を使える人ならオンラインで読むことができます。たとえば中央公論社からでていた世界の名著と続世界の名著シリーズには、多くの名著の翻訳がはいっていて、全部オンラインで読むことができます。このブログでも以前、ワトソンとクリックのDNA二重らせんのNatureにのった論文の日本語訳とか、ニュートンのプリンシピア、メンデルの雑種植物の研究などが世界の名著に含まれていると紹介したことがあります。ただ世界の名著、続世界の名著のどの巻になにが訳されているのかを探すのが面倒でした。ネット検索してみるとこちらのサイトに、どの巻に何が訳されているかがわかるようにまとめてくださっているのがわかりました。
https://www.philosophyguides.org/data/great-books-of-the-world/
たとえば科学関係の巻の目次は以下のようになっています。
世界の名著65 現代の科学1
ドルトン「化学の新体系」(廣重徹訳)
ラプラス「確率についての哲学的試論」(樋口順四郎訳)
ヘルムホルツ「力の保存についての物理学的論述」(高林武彦訳)
リーマン「幾何学の基礎をなす仮説について」(近藤洋逸訳)
マックスウェル「原子・引力・エーテル」(井上健訳)
マッハ「認識と誤謬」(井上章訳)
ボルツマン「アトミスティークについて」(河辺六男訳)
ボルツマン「理論物理学の方法の輓近における発展について」(河辺六男訳)
パブロフ「条件反射」(千葉康則訳)
メンデル「植物の雑種に関する実験」(山下孝介訳)
世界の名著66 現代の科学2
プランク「物理学的世界像の統一」(河辺六男訳)
ポアンカレ「科学と仮説」(静間良次訳)
ヒルベルト「公理的思考」(静間良次訳)
アインシュタイン「物理学と実在」(井上健訳)
アインシュタインほか「科学者と世界平和」(井上健訳)
ボーア「原子物理学における認識論的諸問題にかんするアインシュタインとの討論」(井上健訳)
ハイゼンベルク「量子論的な運動学および力学の直観的内容について」(河辺六男訳)
シュレーディンガー「量子力学の現状」(井上健訳)
ノイマン「人工頭脳と自己増殖」(品川嘉也訳)
ウィーナー「科学と社会」(鎮目恭夫訳)
ワトソン、クリック「デオキシリボ核酸の構造」(井上章訳)
マッカロー「なぜ心は頭にあるか」(品川嘉也訳)
キスホルム「精神の未来」(井上章訳)
セント=ジェルジ「医学の将来」(井上章訳)
レダーバーグ「人間の生物学的未来」(井上章訳)
私はどちらの巻ももっていてときどき読んでいます。世界の名著シリーズの解説は、新書一冊分くらいのボリュームがあるので読み応えもありおすすめです。
皆さんも、是非このサイトをみて、ご自分の興味のある巻を、国立国会図書館の個人送信資料で読んでみてください。100分de名著にとりあげられている本もかなりこのシリーズに入っているのがわかると思います。このサイトのトップページもおすすめです。https://www.philosophyguides.org/
このサイトの著者についてはこちら。https://www.philosophyguides.org/about/