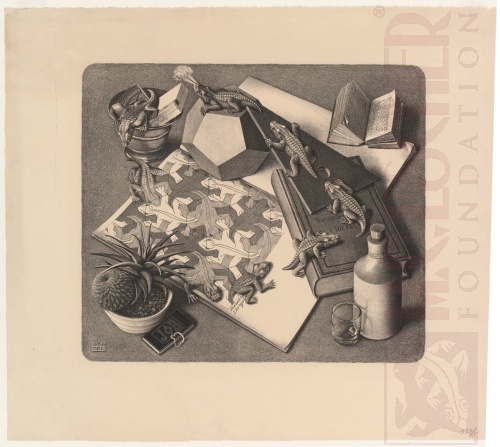nitter.netが復活しています!また他のnitter のインスタンスも使えるものが増えているようです。今日Nitter instance healthのサイトに久しぶりにいって知りました。
Nitter instance healthのサイトをご覧ください。
https://status.d420.de/
今日現在動いているのは以下のインスタンスです。英国王立協会のアカウントにアクセスしてみました。
https://nitter.space/royalsociety
https://lightbrd.com/royalsociety
https://nitter.privacydev.net/royalsociety このインスタンスでは、アカウントがフォローしているアカウントも見ることができます。followingのリンクをクリックしてみてください。429 Too Many Requestsのエラーになることが多いので常用はきびしそうです。どうしてもフォローしているアカウントを見たいときは、TorなどでIPアドレスを変えて再度アクセスすることも必要かと思われます。
https://nitter.net/royalsociety
https://xcancel.com/royalsociety
https://nitter.poast.org/royalsociety このインスタンスはブラウザチェックで古いブラウザをはじくようになりました。⇒古いブラウザも受け付けるように設定が戻されたようです‥‥(25/02/28)。
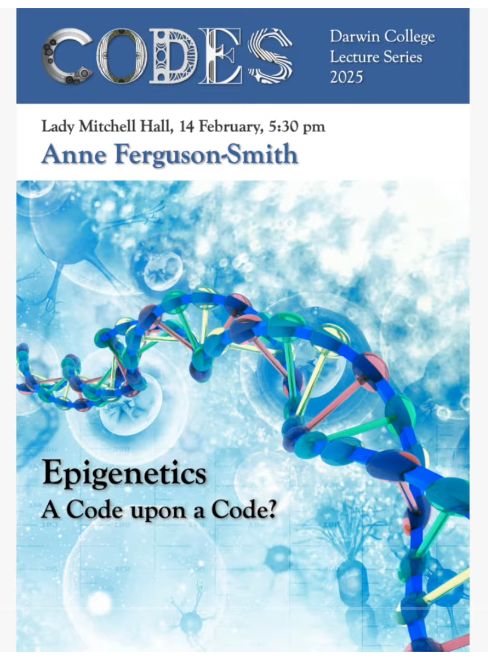 Epigenetics: A Code upon a Code? – Professor Anne Ferguson-Smith
Epigenetics: A Code upon a Code? – Professor Anne Ferguson-Smith