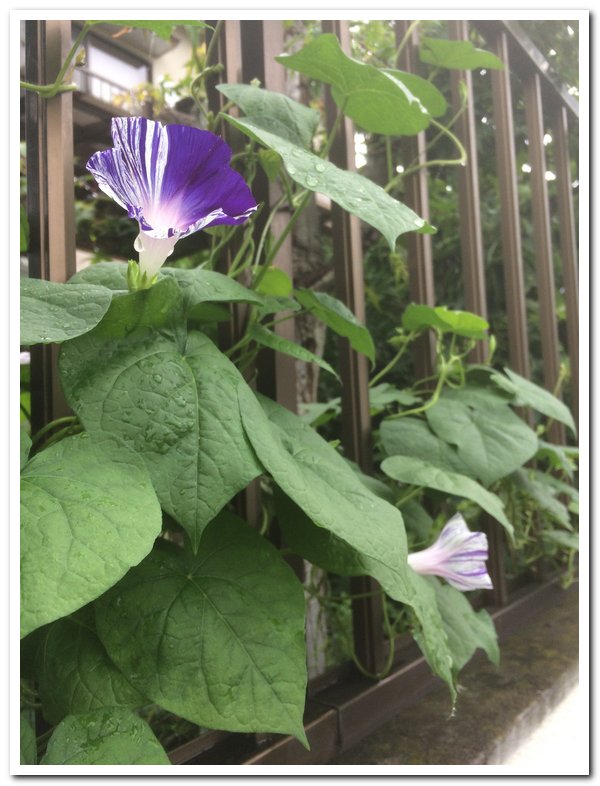国立国会図書館デジタルコレクションで読める本の紹介(第32回):
国立国会図書館の個人送信資料で閲覧できる本が大量に追加されました。
『国立国会図書館デジタルコレクションに図書等約14万点を追加(2025年06月27日)』
https://current.ndl.go.jp/car/254879
今日は一日中 ChatGPTで作業していたので、記事は追加された本をいくつか紹介するだけにします。
347) L.シュワルツ 著 ほか『物理数学の方法』,岩波書店,1966. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1382091 (参照 2025-06-28)
348) 竹内外史 著『数学から物理学へ』,日本評論社,1979.3. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/12592237 (参照 2025-06-28)
349) 森毅 著『位相のこころ : 位相空間論と関数解析のために』,現代数学社,1975. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/12622915 (参照 2025-06-28)
350) H.F.ジャドソン 著 ほか『分子生物学の夜明け : 生命の秘密に挑んだ人たち』上,東京化学同人,1982.2.. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/12604776 (参照 2025-06-28)
351) H.F.ジャドソン 著 ほか『分子生物学の夜明け : 生命の秘密に挑んだ人たち』下,東京化学同人,1982.2.. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/12604779 (参照 2025-06-28)
352) ジョン, M.トーマス 著 ほか『マイケル・ファラデー : 天才科学者の軌跡』,東京化学同人,1994.12. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/13153886 (参照 2025-06-28)
353) 丸山工作 編『夢と真実 : 生物学者は語る』,学会出版センター,1979.12. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/12603119 (参照 2025-06-28)
354)『わが人生観』1,大和出版販売,1972. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/12467196 (参照 2025-06-28)
355) 岡潔 著『日本のこころ』,講談社,1967. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2934439 (参照 2025-06-28)
356) 浅見定雄 著『にせユダヤ人と日本人』,朝日新聞社,1986.12. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/12218775 (参照 2025-06-28)
357) イザヤ・ベンダサン 著『日本人とユダヤ人』,山本書店,1970. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/12247565 (参照 2025-06-28)