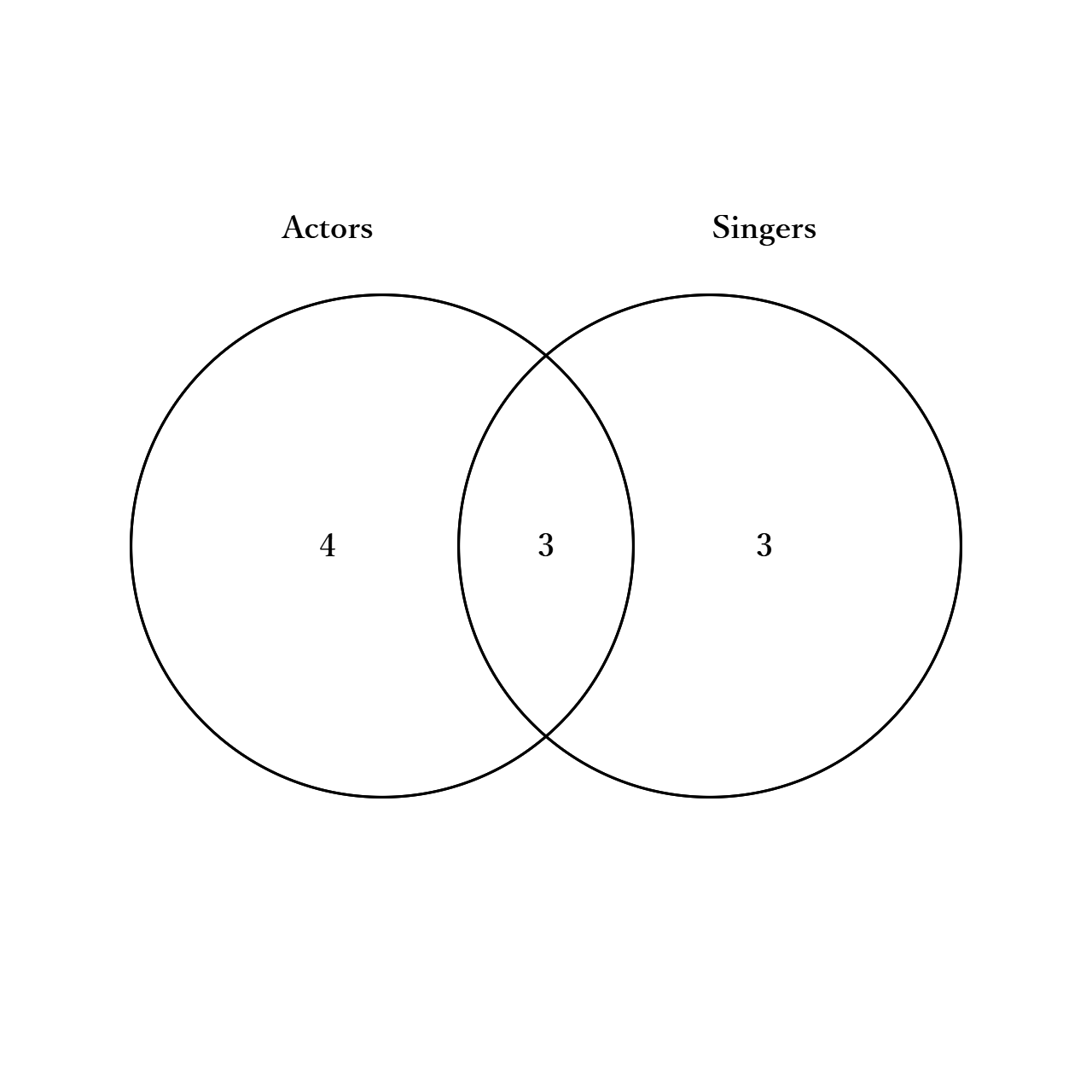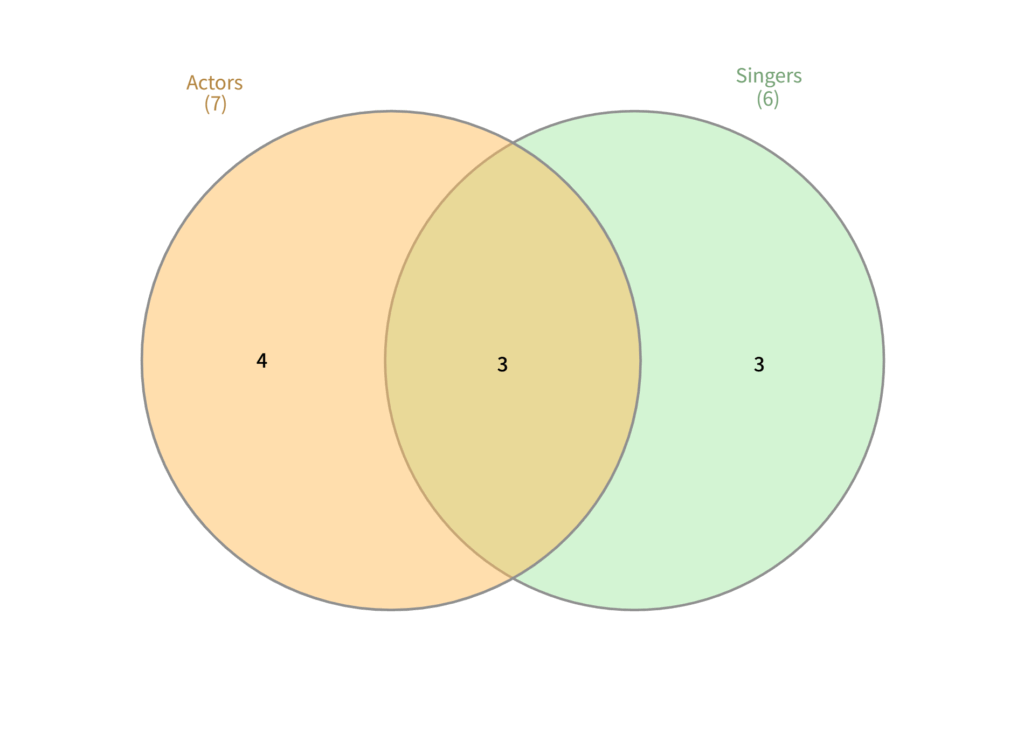iPadのOSアップグレードとAffinityのソフトウエアの無料でのインストールをやってみました。
私のiPadの空き容量が少なくて、最新版のAppleのOS18.7.1をインストールするのに必要な11GBあまりの空きがありませんでした。それで長いあいだOS17からアップグレードせずに放置していました。今回、使いにくいiTuneを使ってアップグレードを実行してみたのでメモしておきます。
最新版のiTuneをWindows10のPCにインストールしてPCにバックアップをとっておき、iPadにあるディスク容量を食っているKindleやその他の電子書籍リーダーのデータを削除、その後iTuneをつないでWindows10上で動くiTuneでiPadOSをアップグレードしました。その後、Kindleのデータや電子書籍リーダーのデータを戻して無事アップグレード完了しました。
注意点がいくつかあります。
1)iTuneは絶対Microsoft Storeからインストールしてはいけません。Appleの公式ページにいってもMicrosoft Storeからインストールするように書いてありますがこれは禁物です。https://www.apple.com/jp/itunes/にいって、下の方にある、「ほかのバージョンをお探しですか?MacOS>, Windows>」の部分でWindowsをクリックします。すると新しいページが開くので、「今すぐWindows用のiTunesをダウンロード(64ビット版)」をクリックしてダウンロードしてください。Microsoft Store版のiTuneはUWP(ユニバーサルWindowsプラットフォーム)アプリといわれるもので、Appleの提供するiTuneに付随するサービスなどが欠けているようです。私は最初これをインストールしたのですが、iPadをUSBケーブルでつないでも時々しか認識してくれず、また認識してもかならず0xE800000Aエラーが出て使い物になりませんでした。Microsoft Store版のiTuneを完全にアンインストールした後、上のApple版のiTuneをインストールすると、うそのようにエラーが消えてスムーズにバックアップが作成できました。電子書籍版のデータもアプリがiTuneに対応していたため、データをPCにバックアップできてよかったです。
2)このバックアップですが、昔はバックアップを日付管理していたのでバックアップは複数個PCに保持できて、どのバックアップから復元するかはプルダウンメニューで選べました。久しぶりにiTuneを使ってみて驚いたのは、バックアップは一つだけしか保持されないように仕様変更されていたことです。新しいバックアップをとると、前のバックアップは上書きされて消えてしまいます!保存しておきたければ、バックアップを別の場所にコピーして保存しておき、復元する時に元のフォルダに戻すようにする必要があるのです。これは重要ですので覚えておいてください。
たとえば、iPadのバックアップ後、Kindleや電子書籍、写真データなどを削除して空き容量が増えたiPadをつなぐと、iTuneがiOSのアップグレードができますがやりますか?ときいてきます。「はい」でアップグレードを始めるとバックアップをとりますか?ともきいてきます。バックアップするを選んでしまうと、1)で復元のためにつくっておいたバックアップが、空き容量の増えた今回PCにつないだiPadのバックアップで上書きされてしまうので注意してください。上に述べたように、昔は上書きしなかったので今回、バックアップが消えてしまっていてびっくりしました。コピーしてとっておいたバックアップにバックアップを入れ替えれば復元できます。
3)Kindleのファイル削除については次の方法をおすすめします。
KindleのiPadアプリの場合、ソフト本体は残しておいてライブラリの本を複数選択してアクションメニューから『この端末から消去』を選んでファイルだけ削除しておくと復元にとても便利です。削除した本のファイルは消えますが本のアイコンは残ったままでチェックが入っていない状態になります。ライブラリには端末から削除された本のアイコンが残っていますので、どんな本がライブラリにあったかが一目瞭然です。バックアップを誤って上書きしてしまったとしても、Kindleのライブラリにある本の表紙などのイメージをクリックすれば、Amazonから再ダウンロードされてまた読めるようになります。Kindle本の削除は「この端末から削除」を使うことがおすすめです。
iPadの空き容量が増えたので、今話題のAffinityのiPad版(AdobeのPhotoshopなどのソフトに似たソフトであるAffinity Photo 2, Affinity Designer 2, Affinity Publisher 2)の無料でのインストールを試してみました。これら3つのiPad版のソフトが無料で使えるようになると評判です。今晩やってみたらまだ3本とも、0円で購入できたので必要な方は是非ためしてみてください。それぞれ1ギガ以上のサイズのソフトですので空き容量が減りますが Affinity Photo 2, Affinity Designer 2, Affinity Publisher 2の3本のソフトが無料で永久ライセンス取得できました。
やり方はこちらのサイトをご覧ください。一つ入れてしまえば、あとの2本のインストールと永久ライセンス取得(0円での購入)はスムーズにすすみます。
【10/30まで?】買い切り2,440円×3本のデザインアプリが無料!Affinityを今すぐゲットする方法
https://note.com/n_studio/n/ndf958b4a0225