今年の3月の記事(本記事の末尾参照)で、生化学入門におすすめの教科書と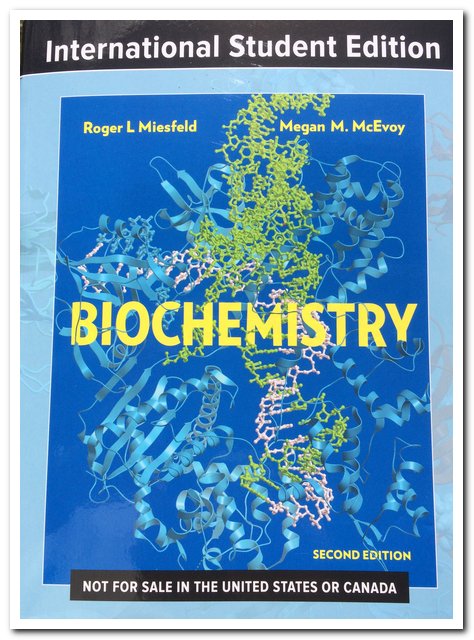 して、ミースフェルド生化学(東京化学同人)を紹介しました。生化学を学び始めた方には日本語版をおすすめします。日本生化学会の推薦教科書です。これは初版の日本語版ですが、2021 年に第二版がでています。Amazonでこの第二版の中古本が安かったので購入し、一昨日 本が自宅にとどきました。International Student Editionという米国内とカナダでは販売できないタイプの版本でした。税込8000円ちょっとの値段がついていたので、即ショッピングカートにいれて購入しました。未読本と書かれていたのですがたしかに届いたものは未読本でした。ebookがついているのかと思いましたが、表紙の裏にスクラッチがついていて、それを削るとネットでの登録コードがあらわれてそれで出版社のサイトで登録すると、オンライン版のBiochemistryが読めるようになっていました。オンライン版は紙の本よりきれいで見やすいので良いと思いました。ただオンラインで読んでいるときにLife Science Dictionaryはひけませんでした。また単語を選択して訳がポップアップするFirePOP!も動きません。コピー回数を計測するような仕組みになっているようで、日本人がオンライン辞書を引きながら読むのには向いていないようです。Kindle版もないようですのでちょっと残念です。なおPDICは動くのでコピーすると訳がポップアップするのは確認できました。
して、ミースフェルド生化学(東京化学同人)を紹介しました。生化学を学び始めた方には日本語版をおすすめします。日本生化学会の推薦教科書です。これは初版の日本語版ですが、2021 年に第二版がでています。Amazonでこの第二版の中古本が安かったので購入し、一昨日 本が自宅にとどきました。International Student Editionという米国内とカナダでは販売できないタイプの版本でした。税込8000円ちょっとの値段がついていたので、即ショッピングカートにいれて購入しました。未読本と書かれていたのですがたしかに届いたものは未読本でした。ebookがついているのかと思いましたが、表紙の裏にスクラッチがついていて、それを削るとネットでの登録コードがあらわれてそれで出版社のサイトで登録すると、オンライン版のBiochemistryが読めるようになっていました。オンライン版は紙の本よりきれいで見やすいので良いと思いました。ただオンラインで読んでいるときにLife Science Dictionaryはひけませんでした。また単語を選択して訳がポップアップするFirePOP!も動きません。コピー回数を計測するような仕組みになっているようで、日本人がオンライン辞書を引きながら読むのには向いていないようです。Kindle版もないようですのでちょっと残念です。なおPDICは動くのでコピーすると訳がポップアップするのは確認できました。
本の内容は、生化学入門に最適の読みやすいいい本です。初版以降の生化学の発展ももりこまれて、さらに動画やPDBのデータなども活用して生化学が学べるようになっています。また生化学の反応機構についても増補されているようです。英語自体はやさしいし、興味深いエピソードをまじえながら、読んでいける本になっていますので、学部生や修士の人は、この英語の第二版にチャレンジしてみるのもよいと思います。おすすめの本です。
これは余談ですが、アマゾンの中古本は、一度アクセスして値段を確かめた後、しばらくしてそれを買うことにきめて再アクセスすると値段が数時間前にアクセスした時よりつりあがっていることがよくあります。それも各出品者一斉にあがっているのです。以前Molecular Principles of Animal Developmentという授業でよく使っていた教科書を再度購入しようとしたとき、このような体験をしました。結局 再度購入はやめて、Internet Archiveで読んでいます。Amazonで中古本を購入するときには、値段をメモしておくこと、これは買おうかなとまよっているときにはショッピングカートにいれておくことをお勧めします。ショッピングカートにいれた本も値段がつりあがるのでしょうか。その辺のところも気を付けておきたいものです。
(以下は2022/3/21の記事の再録です。)
今日は生化学のおすすめ教科書を紹介します。翻訳書で「ミースフェルド生化学」(東京化学同人)という本です。日本生化学会のおすすめ教科書です。はじめて生化学をしっかり学ぼうと考えている人のために、翻訳者の先生たちが、訳語と英語をともに掲載するようにするなどいろいろ工夫も凝らされていて、この本を一冊読めば原著論文も読めるようになるすぐれた教科書です。出版社のサイトで立ち読みもできますし、推薦の書評も掲載されているのでご覧ください。2017年発行の教科書の翻訳ですが、まず慣れ親しんだ日本語で生化学を学べる上に、生化学の専門語を英語も一緒に学べるので、生化学を初めて学ぶ人にしっかりとした基盤をこしらえることができる教科書です。勉強の仕方としては、まず日本語版を読むのを強くすすめます。原著の第二版(2021年発行の英語版)はまだペパーバック版がでておらず高いのでおすすめしません。まずこの日本語版を読み終えてから、今後発行される第二版のペーパーバック版を読めば、自分の英語読解力が驚くほど進歩しているのを実感できると思います。

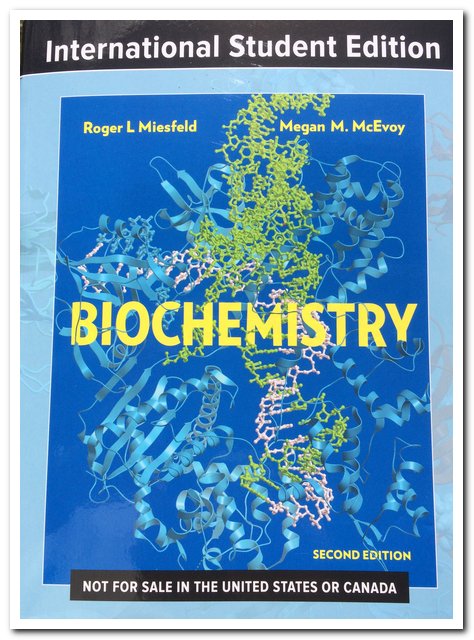 して、ミースフェルド生化学(東京化学同人)を紹介しました。生化学を学び始めた方には日本語版をおすすめします。日本生化学会の推薦教科書です。これは初版の日本語版ですが、2021 年に第二版がでています。Amazonでこの第二版の中古本が安かったので購入し、一昨日 本が自宅にとどきました。International Student Editionという米国内とカナダでは販売できないタイプの版本でした。税込8000円ちょっとの値段がついていたので、即ショッピングカートにいれて購入しました。未読本と書かれていたのですがたしかに届いたものは未読本でした。ebookがついているのかと思いましたが、表紙の裏にスクラッチがついていて、それを削るとネットでの登録コードがあらわれてそれで出版社のサイトで登録すると、オンライン版のBiochemistryが読めるようになっていました。オンライン版は紙の本よりきれいで見やすいので良いと思いました。ただオンラインで読んでいるときにLife Science Dictionaryはひけませんでした。また単語を選択して訳がポップアップするFirePOP!も動きません。コピー回数を計測するような仕組みになっているようで、日本人がオンライン辞書を引きながら読むのには向いていないようです。Kindle版もないようですのでちょっと残念です。なおPDICは動くのでコピーすると訳がポップアップするのは確認できました。
して、ミースフェルド生化学(東京化学同人)を紹介しました。生化学を学び始めた方には日本語版をおすすめします。日本生化学会の推薦教科書です。これは初版の日本語版ですが、2021 年に第二版がでています。Amazonでこの第二版の中古本が安かったので購入し、一昨日 本が自宅にとどきました。International Student Editionという米国内とカナダでは販売できないタイプの版本でした。税込8000円ちょっとの値段がついていたので、即ショッピングカートにいれて購入しました。未読本と書かれていたのですがたしかに届いたものは未読本でした。ebookがついているのかと思いましたが、表紙の裏にスクラッチがついていて、それを削るとネットでの登録コードがあらわれてそれで出版社のサイトで登録すると、オンライン版のBiochemistryが読めるようになっていました。オンライン版は紙の本よりきれいで見やすいので良いと思いました。ただオンラインで読んでいるときにLife Science Dictionaryはひけませんでした。また単語を選択して訳がポップアップするFirePOP!も動きません。コピー回数を計測するような仕組みになっているようで、日本人がオンライン辞書を引きながら読むのには向いていないようです。Kindle版もないようですのでちょっと残念です。なおPDICは動くのでコピーすると訳がポップアップするのは確認できました。 昨日は英語のAlphaFold2の講演動画などを紹介しました。日本語の総説ですが、東京大学の森脇 由隆先生が書かれたオープンアクセスの総説がおすすめです。
昨日は英語のAlphaFold2の講演動画などを紹介しました。日本語の総説ですが、東京大学の森脇 由隆先生が書かれたオープンアクセスの総説がおすすめです。