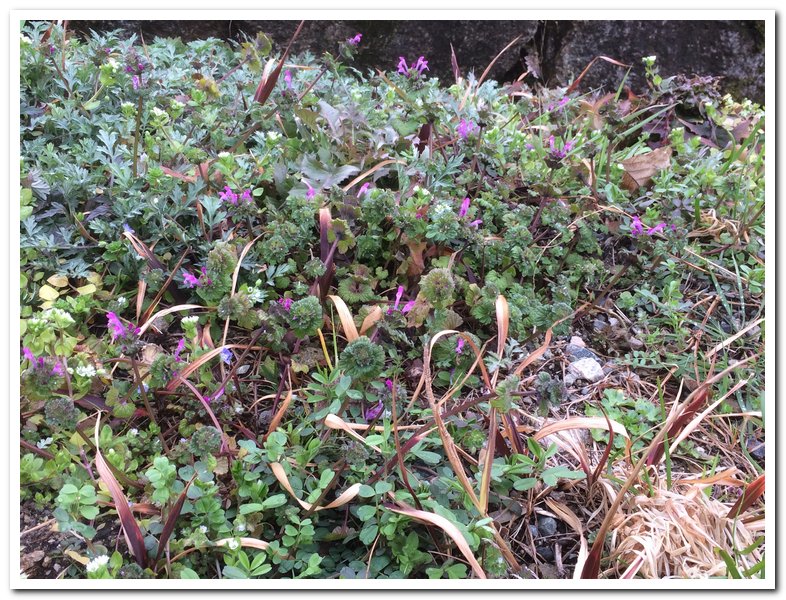今日は科学史の話題です。アリスタルコスという紀元前に生きた古代ギリシャの科学者がいます。地球の大きさや、地球と月、太陽までの距離なども巧妙な方法で求めています。
そのやり方をわかりやすく解説している動画があったので紹介します。
地球と月、そして太陽がそれぞれどのくらい離れているか、大きさはどれほどかなどを古代ギリシャ人が測定した方法が次の動画でわかりやすく解説されています。
The Ancient Mathematician who Measured the Sun
https://youtu.be/shkcVDHOvAI?
動画の中に出てくる本はInternet Archiveで貸出可能なので借りて読むことができます。ダウンロードすることはできませんが、同じ本の古いバージョンはダウンロードできるのでやってみてください。本のタイトルは
Aristarchus of Samos, the ancient Copernicus; a history of Greek astronomy to Aristarchus, together with Aristarchus’s Treatise on the sizes and distances of the sun and moon
ダウンロードできるサイトはこちらです。
https://archive.org/details/aristarchusofsam0000heat/mode/1up
アリスタルコスの現存している著作の翻訳もあります。国立国会図書館デジタルコレクションで読むことができます。
世界の名著9 ギリシャの科学
国立国会図書館デジタルコレクション
https://dl.ndl.go.jp/pid/12406073
この動画のチャンネルにあった次の動画も面白そうです。アルキメデスの失われていた著作『方法』が如何に発見されて解読されたかという有名なお話です。
The $2 Million Lost Book of Archimedes
https://youtu.be/ZXNIgHov0Nk?